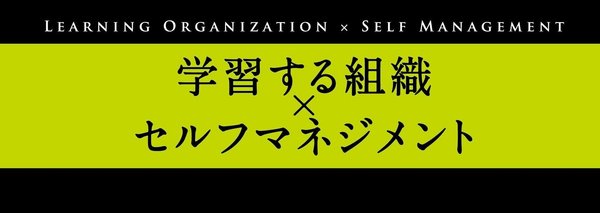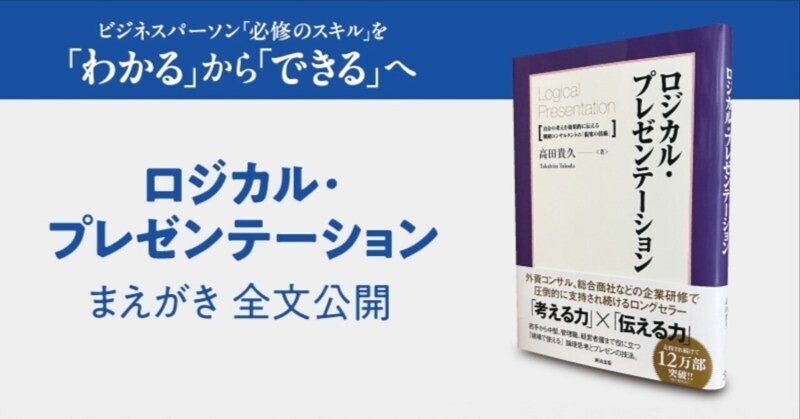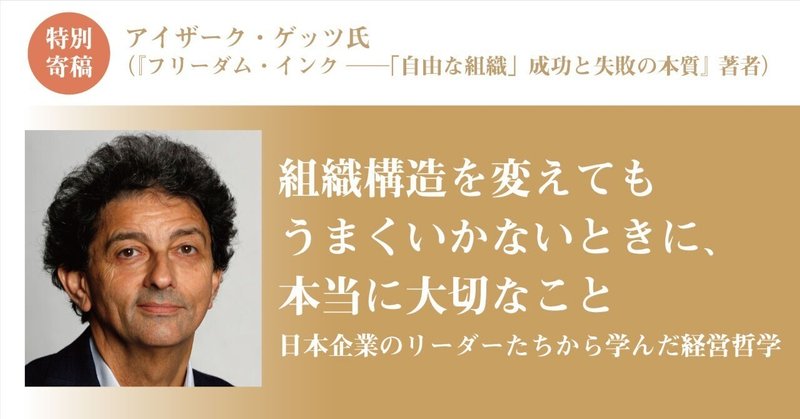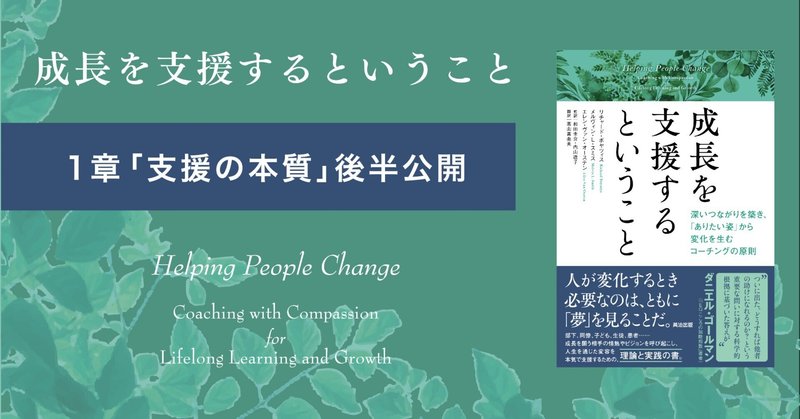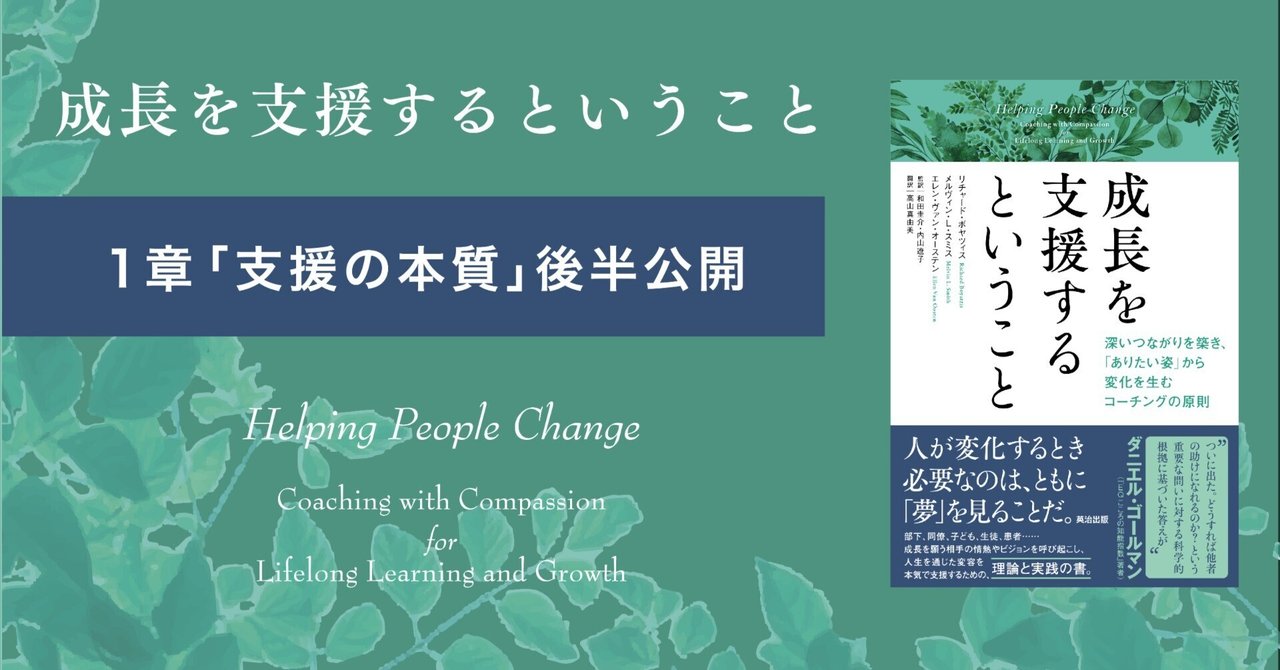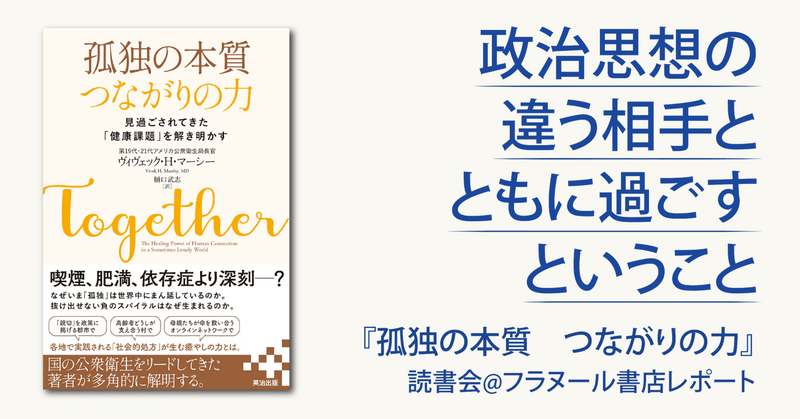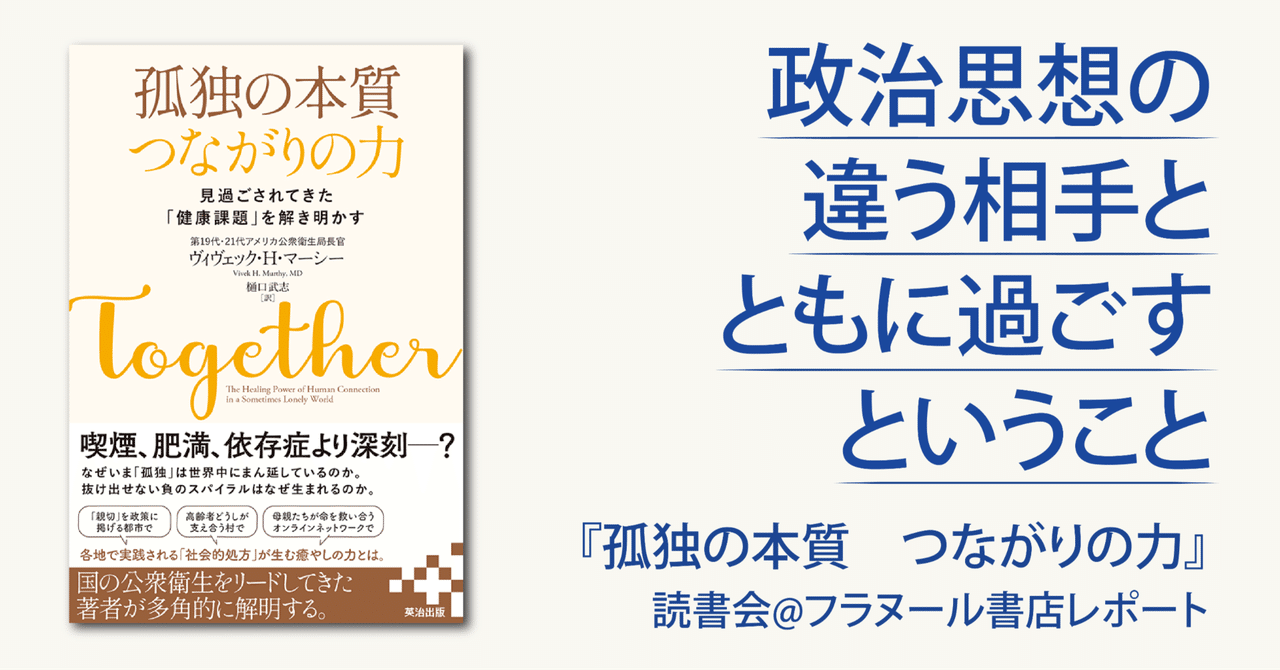英治出版オンライン
英治出版の書籍をより楽しむコンテンツ、よりよい未来をつくるアイデア、読者を応援する企画…
最近の記事

プロジェクトの成否を左右する、「創造の源(ソース)」とは?──『ソース原理[入門+探求ガイド]』より「訳者まえがき」を公開!
どうして私たちは、「仕事でやりたいことなんてできるはずがない」と自分を過小評価してしまうのでしょうか? どうすれば、組織で、チームで、プロジェクトで、お互いが自分らしく生き生きといられるような協力関係をつくることができるのでしょうか? 私たちはこれまで、20年以上にわたってさまざまな組織を支援する中で、どの組織も「協力関係」の問題を抱えていることを目の当たりにしてきました。 青野は、税理士として帳簿をチェックするだけでなく、「経営の現場でどうすれば1人ひとりがお金への囚