
なぜある人は失敗に押しつぶされ、別の誰かは耐え抜けるのだろう。(村瀬俊朗:早稲田大学准教授)
遠藤章博士をご存じだろうか。コレステロール値を低下させるコレステロール合成阻害剤の1つ「コンパクチン」を発見した科学者である。
コンパクチンは、三大死因の2つである「冠動脈疾患」と「脳血管疾患」の予防と治療に有効な合成物質と言われ、この疾患に苦しむ患者は国内で1450万人にのぼる[1]。遠藤は当時、三共株式会社(現第一三共株式会社)に勤め、現在はバイオファーム研究所の所長だ。
コンパクチンの発見は容易ではなかった。1971年、遠藤は仲間と共にコレステロール値を低下させる物質をキノコやカビから探索することにした。当時、コンパクチンはまだ発見されていなかったが、遠藤はコレステロールの合成を阻害する「何か」を、カビやキノコが作り出すと考えた。実に6000株のカビやキノコを2年の歳月をかけて調査。
この長い道のりで、遠藤は常にプロジェクトの頓挫を恐れ、「発見できなければ研究を中止する」と心に決めていた。そして研究開始から2年後の1973年、ついに遠藤たちの努力が実り、ある青カビが後にコンパクチンとなる「何か」を保有することを発見した[2]。
しかし、この発見が終わりではなかった。コンパクチンが低毒素であることと、コレステロール値低下の促進機能を持つことが示せなければ、新薬の基礎として認められない。残念なことに、初期試験の結果、ラットのコレステロール値が低下しないことが明らかになった。
それから更に3年の月日が流れ、遠藤は研究の中止か継続か、決断を迫られていた。「どうせ止めるなら、せめてコレステロール値が低下しない原因を突き止めてからだ」と考え、継続を決断。最悪の状況を妻に説明すると理解を示してくれた。上司に辞職を求められたときに潔くいられるよう、辞表を常に懐に忍ばせていたという。
1974年から1976年にかけて、遠藤はコレストロールが低下しない原因を究明すべく一心不乱に調査を続けた。この頃、社内からは遠藤の研究に懐疑的な目が向けられていたが、彼が勤める研究所の有馬洪所長だけは一貫して遠藤たちの試みを支持し、社内の圧力から守っていた。
実験はうまく行かず、打開策も見当たらない1976年1月は特に寒い月だった。遠藤は研究に疲れ、帰宅途中のいつもの居酒屋で一杯やっていると、三共の別の研究所に勤める北野訓敏博士にばったり会った。北野は鶏を用いて農薬の実験を行っていたが、2月に彼の研究は終了となる。そのため鶏の処分について話し、「終わったら焼き鳥にでもしよう」と冗談を言っていた[3]。
その時、ふと遠藤の頭にアイデアが浮かんだ。
北野博士の鶏は高齢であり、コレステロールを大量に含む卵を毎日生むため、おそらく体内のコレステロール値は高い。一方で、これまで検査に用いていたラットはコレステロール値が正常だった。コレステロール値が高い鶏ならば、コンパクチンの効果が期待できるかもしれない。
この考えを北野に提案すると、彼は二つ返事で引き受けてくれた。
結果は見事なコレステロール値の低下──しかも34%の低下であった[4]。
★
新しい挑戦に乗り出すとき、誰しも遠藤のような失敗の連続に心が押しつぶされそうになる。それでも重圧に耐えながら必死にアイデアの実現に向けてひた走る。あなたもその一人ではないだろうか。
ここで疑問が生じる。なぜある人は失敗に押しつぶされ、別の誰かは耐え抜けるのだろう。挑戦には失敗が付きまとうため、失敗を耐え抜くメカニズムを理解する必要がある。失敗の際に人間の心理はどのように機能し、どのように防衛するかを考えたい。
「自分が自分をどう捉えているか」の仮説
創造的な自分。さぼってしまう自分。陽気な自分……。
私たちは社会の中で、様々な活動から経験を蓄積する。経験とは、自身の過去の行動、思考、感情が心に残った状態であり、これらの経験を通して私たちは自分自身が何者かを理解する。
例えば、つらい練習を耐え抜きやり切った経験をした人は、耐え抜いた自分が心に焼き付く。そして、自分がどういう人物かを考えたとき、記憶に容易に浮かび上がるその「やり抜いた過去」が、自分自身を定義づける1つの重要な要素となる。
「自分とは何か」
この問いは常に私たちの傍に存在し、自身をうまく言い表す自己イメージを多用な経験を通じて育んでいく[5]。自分自身を捉える自己イメージは心理学の言葉で「セルフ・コンセプト」と呼ばれ、私たちが行動する際の指針となる。
例えば、新しいプロジェクトを始める際、「困難に耐え抜いて力を発揮できる」があなたのセルフ・コンセプトならば、あなたはこれをもとに新しい仕事や環境と対峙する。新しい人や地域、知識を学習する中で決して臆病にならず、「自分であれば新しい場所でも実力を発揮できる。いつも通り頑張ろう」と胸を張って取り組むだろう。一方、セルフ・コンセプトがそうした前向きのものではない場合は、困難を乗り越える自信が生まれず、不安に掻き立てられ、最初の一歩を踏み出せずに終わってしまうかもしれない。
ウェスターン・シドニー大学のマーシュ教授とペリー教授は、国際競泳大会の参加者275名のデータをもとに検証した結果、(個人の過去の成績を加味しても)セルフ・コンセプトが大会の成績に影響することを突き止めた[6]。
彼らは、「競技者としての自分の肉体や精神力の評価」が競技で力を発揮するために重要なセルフ・コンセプトと考え、以下の6つの要素を測定した。
1.スキル・レベル:本大会での私の競技技術はいつもより良好である。
2.肉体の適合性:本大会に合わせて、私は自分の実力が発揮できるような体を仕上げている。
3.有酸素運動:私の持久力は本大会での最大の武器である。
4.無酸素運動:コーチやライバルは、私の無酸素運動における能力を高く買っている。
5.精神力:本大会において、状況に応じて意図的に自身のやる気を引き出せる。
6.パフォーマンス:実力をいかんなく発揮できるため、本大会では成功するだろう。
これら6つの要素の平均数値が、「競技者としての自己評価」を表している。検証の結果、数値の高さは大会の成績に影響した。競技者としての自己評価が高い選手、すなわち自信を帯びたセルフ・コンセプトをもつ選手は、実力ある競技者として自身を認識しているため、余計な雑念なく競技に向き合うことができる。一方で、自信を削いでしまうようなセルフ・コンセプトの場合、不安に駆られ、能力を出し切れずに終わってしまう。
セルフ・コンセプトとは、自分が自分をどう捉えているかの仮説であり、様々な環境下で私たちの行動を導いてくれる。
相反する経験を持つ私たちが正のセルフ・コンセプトを維持するには?
一筋縄ではいかないプロジェクトにおいて、「自分はできる」というセルフ・コンセプトが定着していても、失敗が重なり「自分はダメだ」というセルフ・コンセプトが浮上してしまうと、困難を乗り越える力が失われる。
そのため、新しい挑戦の過程で失敗したとしても、ポジティブなセルフ・コンセプトを維持する必要がある。つまり失敗という現実とは真逆の、正の状態を保たねばならないのだ。
私たちは豊富な経験を蓄積するため、セルフ・コンセプトには複数の側面が存在する。あなた自身も、耐え抜き成功を収めた経験もあれば、失敗した経験もあるだろう。セルフ・コンセプトは呼び起こされやすい経験に強く影響される。失敗した経験があっても、主となる記憶要素が成功体験であれば、「困難でもやり抜く自分」が意識されやすいだろう。
しかし失敗した経験も心の奥隅に存在するため、一時的にでも失敗した経験が強く呼び起こされると、セルフ・コンセプトの負の側面が際立ち、自己評価の低下を招く。
繰り返しになるが、セルフ・コンセプトは呼び起こされやすい経験に強く影響される。したがって、失敗の記憶が恒常的に呼び起こされない限りは、「困難でもやり抜く自分」が主であるため、セルフ・コンセプトは正の状態となる。
人は失敗も成功もする。人生には良いことも悪いこともある。そうした相反する経験を持つ私たちがネガティブな経験をした際に、正のセルフ・コンセプトを維持するにはどうすればよいのか。
この疑問を解くために、カナダのウォータールー大学のドッジソン教授とウッド教授は、セルフ・コンセプトの多面性に着目した[7]。
個人が失敗した際、多くの良い経験があっても、一部の失敗が呼び起こされて全体評価を過度に傷つけてしまう。しかし、この失敗の経験はあくまで「現在は失敗している」という限定的なものだ。そのため、良い経験をより強く想起することで、一時的な失敗経験が持つ負の影響を抑え、全体評価を良好な状態に保つことができる。たとえば、他の得意分野や過去の成功体験を強く思い返すことで、セルフ・コンセプトの好ましい状態が維持される。
ドッジソン教授とウッド教授は、「自尊心の高い人は自身の評価維持が得意なため、失敗の際にも得意分野をより強くイメージすることで苦手分野の想起を抑制する」という仮説を立て、72人の大学生を対象に実験を行った。実験の流れはこうだ。
(1)学生が実験室に到着後、彼らの得意・不得意分野と自尊心の高さをアンケートから特定。自尊心が高い36名と、低い36名が実験に参加した。
(2)学生は、与えられた英単語のアルファベットを入れ替えて別の単語に組み替えるアナグラムという作業を行った(例:LISTEN→SILENT)。学生は作業を行う際、「アナグラムの点数が大学での成功を予測する」と伝えられた。
(3)実際のアナグラムの結果にかかわらず、「点数が悪い」か「何も伝えない」の2つのフィードバックを無作為に学生に与えた。アナグラムのフィードバックは、学生に自分は能力が低いと思わせることを目的とした。
(4)学生はどちらかのフィードバックを受けた後に2つ目の作業に入る。この作業では、12分野(学術、音楽的才能、身体能力、リーダーシップなど)から96のフレーズがコンピュータ・スクリーンに表示された。学生は、フレーズが自身に該当するかをキーボードで即座に回答するように求められた。例えば、「良い競技者」や「ダメな競技者」などのフレーズに対して、「自分だ」か「自分でない」の回答を下す。回答速度の記録によって、得意分野と不得意分野に対する反応速度が計測された。
そして学生たちは、以下の4つのカテゴリーに分類された。
(ア)自尊心が高い。点数が悪いことをフィードバック。
(イ)自尊心が高い。何もフィードバックしない。
(ウ)自尊心が低い。点数が悪いことをフィードバック。
(エ)自尊心が低い。何もフィードバックしない。
分析の結果、(ア)の学生は、(イ)の学生よりも、自身の得意分野に対してより素早く反応し、不得意分野への反応は鈍かった。一方で、(ウ)と(エ)の学生は反応に違いがなかった。
自尊心の高い人(セルフ・コンセプトをうまく守れる人)は、自信を削ぐ情報が与えられても、得意分野をより強く想起することで苦手分野から目をそらせられる。つまり、(ア)の学生のようにアナグラムの作業で失敗したとしても、自身の強みに目を向けられる。これが、正のセルフ・コンセプトの維持、すなわち「失敗を乗り越えられる粘り強さ」なのだ。
……と、ここで話が終わればよいが、ドッジソン教授らの研究において考慮しなければならない重要な点がある。彼らが検証したのは、あくまで「単発」の失敗における行動(反応)だった。
しかし私たちが直面する失敗は単発ではなく「連続」である可能性が高い。そのような状況では、たとえ失敗が作業の一部で起きたものに過ぎないとしても、その一部を継続的に叩かれ続けるとセルフ・コンセプトが負に転じかねない。このような状況への対応は、個人の努力だけでは限界がある。
ではどうすれば良いのだろう。
ヒントはリーダーシップ研究にある。
リーダーの謙虚さが悩める部下にもたらすもの
リーダーの配慮や精神的な支援が、部下のストレス軽減や職場への積極的な貢献、そして業績や創造性の向上に寄与することは、長年の研究から明らかになっている[8]。リーダーの行動と部下のセルフ・コンセプト維持の関係性に関するドンピシャのリーダーシップ研究は見当たらなかったが、リーダーの行動がセルフ・コンセプトに影響することは十分に妥当な推測と考えられる。
たとえば、課題解決のためにもがき苦しむ部下をリーダーが勇気づけることで、彼らの意識は負の側面から遠ざかり、過去の努力や本来の能力を思い返すことができる。チームや組織のリーダーは象徴的な存在のため、彼らが支援することの心理的な意味は絶大であり、部下の自己評価は好転する。
このことは、中国の西南大学のヂゥー教授らが行った研究結果からもうかがえる。彼らは、リーダーの謙虚さ(Humbleness)が部下の粘り強さを引き出すことを指摘した[9]。
謙虚なリーダーは、組織の成功は自分の努力だけでなく、他者の力があってこそ達成できると理解している。そのため、周囲の貢献や価値に目を向け、彼らの努力を認め称賛することで部下の自信を引き上げる。そして、彼らが存分に力を発揮できるように社内の環境作りにも力を入れる。
仕事に苦労している部下は自身の能力に懐疑的になりやすい。そんな状況でこそリーダーは部下の価値を認め、居場所を与えることで彼らの存在を肯定する。このようなリーダーの行動は、部下のセルフ・コンセプトの良い側面を際立たせ、粘り強さを引き出す。
ヂゥー教授らは、リーダーの謙虚さと部下のパフォーマンスの関係を検証するため、様々な業界の従業員434名(平均年齢34歳)を対象にデータを集めた。
部下から見たリーダーの行動
・リーダーの謙虚さ(9項目):例「私のリーダーは他者の独創的な貢献に感謝する」
部下自身の行動・心理状態
・業務への熱中度:例「願望を満たす方法を模索するために多くの時間を費やす」
・社内での居場所(6項目):例「私の組織は、社内に居場所があるように感じさせてくれる」
・粘り強さ(9項目):例「自身の業績を再評価し、仕事のやり方を改善し続ける」
リーダーが部下の努力を認め感謝すること(謙虚さ)で、部下は自身の得意な作業に没頭でき(熱中度)、職場に居場所を感じられる(居場所)。そして、リーダーが部下の努力を肯定することで、部下のセルフ・コンセプトの良い側面が活性化し、自信の維持につながる。さらに、部下は業務に粘り強く挑戦できるため、好業績へとつながる。これらのことが、分析の結果明らかになった。
部下が失敗に失敗を重ねても、それはあくまでも現在の取り組みに限ってのことであるため、セルフ・コンセプトへの反映を抑制しなければならない。リーダーは部下が過去の成功経験に目を向けられるよう伴走し、今までの様々な努力や貢献を何度も伝え思い返させることで、彼らのセルフ・コンセプトは好ましい状態を維持できる。
コンパクチンの研究で遠藤の努力が報われない時、社内では彼の研究に対して反発が起こり始めていた。その中で所長だけは遠藤の努力を認め、彼らが研究に従事できる居場所を必死に守った。それは、「自分はまだできる」という遠藤の信念の支えとなっただろう。
遠藤博士のその後
遠藤のコンパクチンの発見は、商業的な成功を収めたと多くの読者は思われたかもしれない。残念ながらそうではなった。
コレステロール値低下の効果は認められたが、その後に毒素の懸念が生じ、遠藤は大規模研究に踏み込めずにいた。そんな中、大阪大学の山本章医師からの依頼で、コンパクチンが初めて患者に投与された。その結果、副作用はほとんど確認されず、コレステロール値は30%ほど低下した。
この結果を受けて、コンパクチンの大規模な臨床実験に弾みがついたかに見えたが、その計画は突然中止された。理由は、犬に対する長期毒素試験において、腸管にリンパ腫が出たという噂が流れたからだ。腫瘍性があるかもしれないコンパクチンは医薬品としてはあまりにも危険だと見なされ、国内の研究の熱は一気に冷めてしまった。
一方その頃、米国ではコンパクチンに非常に近い構造で同じ性質を持つロバスタチンを米国大手製薬会社メルクが研究していた。この研究は成功を収め、1986年にアメリカ食品医薬品局に新薬承認申請が提出され、翌年に異例の速さで承認を受けた。
ロバスタチンをもとに開発されたMevacorや後続商品のZocorは、メルクの歴史の中で最も多くの利益を生み、総売上は9000億円を超えると言われる[10]。
遠藤の上司は、遠藤の研究を懸命に支援し、継続できる環境を整えることでコンパクチンの発見までは漕ぎつけた。しかし、組織の上層部や製薬業界の重鎮たちの支援をまとめることができず、商業的成功には至らなかったのである。
失敗が必然である苦難の道では、私たちは常に自己と自己を否定する現実の間で苦悩する。それを耐え抜くために私たちはセルフ・コンセプトを守り、リーダーも部下を支援し続けなければならない。
さらに、足元(現場の努力)と遠方(その努力を紡ぐ道筋)を同時に見ながら、組織内外の理解と支持を得なければ、真の成功は実現できない。そのことをリーダーは決して忘れてはならない。
●参考文献
[1]遠藤章. (2016). スタチンの誕生──世の中の役に立つ科学者を目指して 70年. 日本農村医学会雑誌, 64(6), 958-965.
[2]遠藤章. (2005). 動脈硬化のペニシリン"スタチン"の発見と開発. 心臓, 37, 681-698.
[3]Bahcall, S. (2019). Loonshots: How to nurture the crazy ideas that win wars, cure diseases, and transform industries. St. Martin's Press.
[4]Endo, A. (2008). A gift from nature: the birth of the statins. Nature Medicine, 14(10), 1050-1052.
[5]Gecas, V. (1982). The self-concept. Annual review of sociology, 8(1), 1-33.
[6]Marsh, H. W., & Perry, C. (2005). Self-concept contributes to winning gold medals: Causal ordering of self-concept and elite swimming performance. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(1), 71-91.
[7]Dodgson, P. G., & Wood, J. V. (1998). Self-esteem and the cognitive accessibility of strengths and weaknesses after failure. Journal of personality and Social Psychology, 75(1), 178.
[8]Montano, D., Reeske, A., Franke, F., & Hüffmeier, J. (2017). Leadership, followers' mental health and job performance in organizations: A comprehensive meta‐analysis from an occupational health perspective. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 327-350.
[9]Zhu, Y., Zhang, S., & Shen, Y. (2019). Humble leadership and employee resilience: exploring the mediating mechanism of work-related promotion focus and perceived insider identity. Frontiers in Psychology, 10, 673-681.
[10]Bahcall, 2019.
構成:山下智也
バナー画像:WikiImagesより
村瀬俊朗(むらせ・としお)
早稲田大学商学部准教授。1997年に高校を卒業後、渡米。2011年、University of Central Floridaで博士号取得(産業組織心理学)。Northwestern UniversityおよびGeorgia Institute of Technologyで博士研究員(ポスドク)をつとめた後、Roosevelt Universityで教鞭を執る。2017年9月から現職。専門はリーダーシップとチームワーク研究。2019年から英治出版オンラインで「チームで新しい発想は生まれるか」を連載中。『恐れのない組織』(エイミー・C・エドモンドソン著、野津智子訳、2021年、英治出版)の解説者。
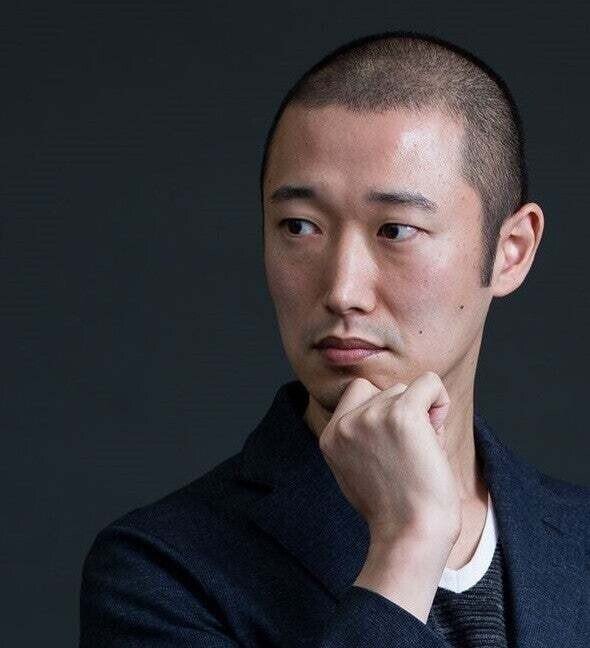
連載:チームで新しい発想は生まれるか
新しいものを生みだすことを誰もが求められる時代。個人ではなくチームでクリエイティビティを発揮するには何が必要なのか? 凡庸なチームと創造的なチームはどう違うのか? 多様な意見やアイデアを価値に変えるための原則はなにか? チームワークのメカニズムを日米で10年以上にわたり研究してきた著者が、チームの創造性に迫る。
第1回:「一人の天才よりチームの方が創造性は高い」と、わたしが信じる理由
第2回:なぜピクサーは「チームで創造性」を生みだせるのか?
第3回:失敗から学ぶチームはいかにつくられるか
第4回:チームの溝を越える「2つの信頼」とは?
第5回:「新しいアイデア」はなぜ拒絶されるのか?
第6回:問題。全米に散らばる10の風船を見つけよ。賞金4万ドル
第7回:「コネ」の科学
第8回:新結合は「思いやり」から生まれる
第9回:トランザクティブ・メモリー・システムとは何か
番外編:研究、研究、ときどき本
第10回:あなたのイノベーションの支援者は誰か
第11回:コア・エッジ理論で、アイデアに「正当性」を与える
第12回:仕事のつながり、心のつながり
第13回:なぜある人は失敗に押しつぶされ、別の誰かは耐え抜けるのだろう。
英治出版オンラインの連載記事やイベントの新着情報は、英治出版オンラインのnote、Facebookで発信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。村瀬俊朗さんの連載マガジンのフォローはこちらから。

