
コア・エッジ理論で、アイデアに「正当性」を与える(村瀬俊朗:早稲田大学准教授)
巨大製薬会社ファイザーに勤めるジョージ・コヘンは、ある日こんな妄想を抱いた。
「社内の優秀な人材が、重要な業務により多くの時間を費やすことはできないだろうか?」
そしてコヘンは2005年、米国の内外に簡単な作業を発注できる社内向けサービス「pfizerWorks」を開発する[1]。コヘンの同僚に試作品を試してもらうと、その多くが気に入り継続を希望した。
しかしpfizerWorksはサイドプロジェクトとして始動したため、費やせる予算と時間に限りがあった。コヘンは社内でより規模の大きいプロジェクトへと昇格させるために奔走していたのだが……
このような状況、あなたも経験したことがあるのではないだろうか。
世界は優れたアイデアで満ちている。しかし多くのアイデアは組織では価値を見出されず、頓挫してしまう。仮にアイデアが試作段階に進んでも、大きなプロジェクトには昇格できずに中止になるケースも多い。
「見たことのないアイデア」こそがイノベーションの条件だと一般的には言われている。しかしケロッグ経営大学院のブライアン・ウジーは、そうした馴染みのないアイデアは組織における「正当性」が理解されず、実現しづらいことを指摘している[2]。
つまり新規性の高いアイデアを必死に探そうとしても、自社の文脈に沿ってアイデアの正当性(そのアイデアが自組織にとって有益である根拠)を示せなければ、努力は泡となってしまうのだ。
そこで今回は、ネットワーク理論の論文を下敷きにしながら、アイデアに正当性を付与するメカニズムに迫りたい。
価値あるアイデアを生む科学者の共通点
創造的なアイデアを生みだし、実現するには「バウンダリー・スパニング(BS)」の活動が効果的だ。BSとは、業界や組織の領域を越えて事業開発や組織変革を行う方法論である。『組織の壁を越える──「バウンダリー・スパニング」6つの実践』(英治出版)には、BSの実践法と豊富な事例が記されている[3]。
BSにおいては一般的に、知識やアイデアの発見に重点が置かれる。だが前述の通り、組織内で馴染みのない知識は、正当性を得づらい。以前この連載で紹介したNIH症候群(外部から持ち込まれる情報、外部で生まれたサービスや製品に対する反射的な拒絶反応)が起きやすいのだ。
※NIH症候群については以下の記事をどうぞ。
インペリアル・カレッジ・ビジネススクールのター・ワルの研究チームは、組織内部にアイデアの正当性と価値を伝達するには「探索と融合」という2つの活動が重要であることを明らかにした[4]。
・探索:異なる業界や環境で活用されており、自分の業界では馴染みのない知識の発見
・融合:外部知識が社内の文脈と合わさり、社内に受け入れられるような価値伝達
そしてワルたちは、探索と融合を独立して行うのではなく、組み合わせることが有効だという仮説を立てた。
この仮説を検証するため、ある多国籍大手企業X社の協力を得て、R&D部署所属の268名の科学者にアンケート調査を実施した。アンケート内容は以下の通りだ。なお、③のイノベーション・パフォーマンスは、部署責任者だけが回答している。
①探索に関する調査
一日の仕事時間を100点とし、社内の関係者(自部署、社内の従業員など)と社外の関係者(大学、専門業者、専門機関などの11の外部領域)のそれぞれにどのぐらいの時間を費やすかを配分してもらう。そして社外に費やす時間をパーセンテージ変換する。1に近づくほど社外への探索活動が活発である。
②融合に関する調査
融合に関する行動データは9項目のアンケートで収集した。例えば以下の通り。
・X社のニーズと外部知識の最適な組み合わせを常に模索しているか?
・外部知識の説明や議論を同僚と頻繁に行っているか?
③イノベーション・パフォーマンス
部門責任者が各科学者の「実行可能かつ価値のあるアイデアを生みだす能力」を評価した。
データ分析の結果、探索のみを行う(探索は行うが融合を行わない)科学者のイノベーション・パフォーマンスは低評価だった。探索のみでは社内の文脈に馴染まず、「実行可能かつ価値のある」アイデアだと認められづらい。
そして、探索のみを行う科学者と比べて、探索と融合の両方を行う科学者はパフォーマンスが高評価だった。外部知識を探索するだけでなく、社内にその価値を伝えることで、自身の考えが正当性を帯びていく。
バウンダリー・スパニングにおいては外部探索に重点が置かれがちだが、アイデアに正当性を付与する活動(融合)をしないのなら、探索に費やす時間と労力は無駄になる。それならば探索などはせず、すでに知っている知識でアイデアを着想したほうが成功しやすいだろう。
さて、創造的アイデアが正当性を勝ち取るには、組織内の文脈との融合が不可欠だ。そこで鍵になるのは、社内の特定のプレーヤーと連携である。次はそのメカニズムを探ってみよう。
組織の創造性が高まる「3つの条件」
常識にとらわれない自由な発想ができるかどうかは、組織のネットワーク上の位置に影響される。例えば既存の枠を越えた着想は、組織運営の中心に位置する人には難しい。組織運営では既存の考えやこれまでの常識を重んじるからだ。一方で、組織の中心ではない淵にいる人物のほうが、外の世界との交流に時間と労力を割きやすく、自由な発想がしやすい。
ニューヨーク大学のカターニとボローニャ大学のフェリアニは、社会ネットワークの「コア・エッジ理論」を用いて、探索と融合のメカニズムを紐解いた[5]。
まずは「コア・エッジ理論」を紹介しよう。
人のつながり(社会ネットワーク)を見える化すると、組織図からは見えてこない重要人物や業務のつながり、そしてネットワークの中心の「コア」と枝先の「エッジ」が浮かび上がる。
図1の業務連携ネットワークの中心にはコアグループがある。コアグループの特徴は、メンバー同士が密に結びつき、他のメンバー(コアではない人たち)とは緩やかなつながりがある。
一方で、ネットワークのエッジに位置するメンバーは緩やかにコアメンバーとの関係を結ぶが、エッジメンバー同士の関係は希薄である。そして、コアとエッジの中間にいるメンバー(ブローカー)は、まさにコアとエッジを結びつけている[6]。
図1:コア、エッジ、ブローカー
コアメンバーは組織内の多くの人と仕事をしている(多数のつながりがある)ため、彼らの意見は組織の隅々まで伝わりやすく、正当性の高い発言として支持されやすい。
だがコアグループ内の密な人間関係は村社会のように機能するため、組織の慣習や伝統的な物の考えを重視させる。同じ考えを持つ者同士が強固に結び付つくと、新しい発想に触れづらくなり、仮に触れたとしてもその価値を見落とす傾向が高い。
一方で、コアから遠ざかるほど人のつながりが弱くなり、組織の慣習への順守性も低下し、新しい情報への感度が高まる。
コアとエッジの中間に位置するブローカーは構造的隙間(ストラクチュアル・ホール)の利点を生かすことができ、創造的発想を育みやすい[7]。人と人のつながりが弱いストラクチュアル・ホールに入り、人をつなげることで、今まで出合わなかった知識をつなげられるので、創造性が高まることが分かっている。そうした利点はあるものの、彼らはネットワークのコアには位置しないため、アイデアの正当性を組織に浸透させることは難しい。
※ストラクチュアル・ホールについては以下の記事をどうぞ。
「コア・エッジ」理論で注目すべきは、グループの中心メンバーが必ずしも組織全体のコアグループに所属しているわけではないという点だ。た6名が所属するグループの課長(図1の左)は、その課内では中心メンバーだが、組織全体ではエッジにいる場合もある。
さて、カターニとフェリアニは、このコア・エッジ理論をもとに、次の3つの条件が成り立つと組織の創造性が高まると仮説を立てた。
(1)ブローカーが探索者の役割を担う(エッジメンバーとの連携によりアイデアを発見・獲得する)
(2)コアメンバーが融合者の役割を担う(ブローカーのアイデアに正当性を付与する)
(3)探索者と融合者がプロジェクトを通して連携する
映画制作者ネットワークから読み解く、創造性が高まる「チーム構成」
カターニとフェリアニはこの仮説を実証するため、映画制作メンバーのネットワークが、映画制作の創造性にいかに影響するかを検証した。
はじめに、ワーナー・ブラザーズなどの大手制作会社が1992~2003年に作成した2,137本の映画制作チームのメンバーのネットワーク図を作成。制作チームのメンバーは、作品の質を左右するプロデューサー、映画監督、ライター、エディター、撮影監督、デザイナー、構成作家、作曲家に絞り、合計11,974名の映画制作ネットワークを完成させた。
図2:映画制作チームのネットワーク図への変換(カターニとフェリアニの図をもとに筆者が手書き) ※□は映画、〇はメンバー
図2のように、映画制作チーム間ではメンバーが重複し、業界には制作過程を共にした人々のネットワークが生まれる。映画制作チームのAとBは、メンバー3によってつながっている。また制作チームのBとCは、メンバー8と9を介してつながっている。
そして、カターニらはこの映画制作ネットワークをもとに次の分析を行った。
・まず、メンバーの位置とコアとの距離を計算し、各メンバーのコア数値を算出。コア数値が高い人をコアメンバー、コア数値が低い人をエッジメンバーとする。
・次に、各チームのコア平均値を算出。
・最後に、各チームのコア数値と創造性の関係を分析するため、各チームの受賞歴(アカデミー賞など)や推薦回数をもとにチーム業績データを作成した。創造的な作品であるほど受賞数が多いと想定し、受賞歴関連のデータを使用したのだ。
以下が分析の結果のまとめである。
・チームのコア数値が高いと業績は高い。
・しかし、コアメンバーが多すぎると業績は低下する。
・また、エッジメンバーが多すぎても業績は低下する。
つまり、コアメンバーを増やしすぎないこと、さらにはエッジメンバーを増やしすぎないことが、チームの創造性(業績)を左右する。では、コアとエッジを半々にすればよいかというと、残念ながらコアメンバーとエッジメンバーの考えには隔たりが大きく、過去のコラボ経験も乏しくチームとしてシナジーを生みだすのが難しい。
そこで浮かび上がってきたのが、ブローカーの重要性である。
前述の仮説の通り、コアメンバーばかりでは伝統的な発想となり、創造性が低下する。エッジメンバーばかりでは斬新なアイデアは出やすいが、アイデアの正当性を業界内で得ることが難しい。ではブローカーはどうか。
ブローカーはエッジメンバーとのつながりから様々な発想に触れることができる(探索)。と同時に、コアメンバーとのつながりがあり、彼らと連携することでアイデアに正当性をもたらすことも可能だ(融合)。
したがって、ブローカーとコアメンバーが互いの立ち位置を理解し、協力し合うことがアイデア実現の糸口となる。
「ブローカーの重要性が浮かび上がってきた」と先ほど述べたが、実はほんとうに重要なのは、コアメンバーの器量なのかもしれない。
ブローカーが組織の伝統からはみ出るアイデアを提案してきたとき、伝統に反すると突っぱねるのではなく、正当性を見出そうとする。そうしたコアメンバーの行為が、創造性の高い組織へと進化する鍵なのではないだろうか。
正当性を与えるつながり
さて、冒頭のpfizerWorksはその後どうなったか。試作品は好評を博したものの、組織全体にサービスを展開するには至らず、開発者のコヘンは突破口を見出せずにいた。
だが転機が訪れた。上級幹部のダビッド・クレターがpfizerWorksに興味を持ち、取引を検討しているいくつかの会社の調査を、投資銀行ではなくpfizerWorksに依頼したのだ。そして調査結果の満足度は高く、予算も低く抑えることができた。
その後、クレターはコヘンに様々なアドバイスを与え、プロジェクト推進のための重要な人物への取次も行った。順調にいっているかに見えたが、再び壁が現れる。コヘンの部署の目的とpfizerWorksの目的が合致しておらず、またコヘン自身の予算規模も少ないことを理由に、全社規模のプロジェクトへの昇格は困難との結論が下されてしまったのである。
だがコヘンとクレターは諦めなかった。議論を重ねた結果、クレターは自身のCommercial Operations部門でpfizerWorksを推進することを決断。組織全体からの注目度は一気に高まり、予算も人材も十分。やがてpfizerWorksは軌道に乗り、6万人以上の従業員の生産性向上に貢献する全社プロジェクトへと成長していったのである[8]。
●参考文献
[1] パディ・ミラー、トーマス・ウェデル=ウェデルスボルグ著、平林祥訳『イノベーションは日々の仕事のなかに──価値ある変化のしかけ方』(英治出版、2014年)
[2] Uzzi, B., Mukherjee, S., Stringer, M., & Jones, B. (2013). Atypical combinations and scientific impact. Science, 342(6157), 468-472.
[3] クリス・アーンスト、ドナ・クロボット=メイソン著、三木俊哉訳、加藤雅則解説『組織の壁を越える──「バウンダリー・スパニング」6つの実践』(英治出版、2018年)
[4] Ter Wal, A. L., Criscuolo, P., & Salter, A. (2017). Making a marriage of materials: The role of gatekeepers and shepherds in the absorption of external knowledge and innovation performance. Research Policy, 46(5), 1039-1054.
[5] Cattani, G., & Ferriani, S. (2008). A core/periphery perspective on individual creative performance: Social networks and cinematic achievements in the Hollywood film industry. Organization Science, 19(6), 824-844.
[6] Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (1999). Models of core/periphery structures. Social Networks, 21(4), 375-395.
[7] Cattani, G., Ferriani, S., & Colucci, M. (2015). Creativity in Social Networks. In The Oxford handbook of creative industries (p. 75). Oxford University Press, USA.
[8] https://www.ft.com/content/c2d551f2-7bf7-11e0-9b16-00144feabdc0
※ヘッダーは、Wilfried PohnkeによるPixabayからの画像
村瀬俊朗(むらせ・としお)
早稲田大学商学部准教授。1997年に高校を卒業後、渡米。2011年、University of Central Floridaで博士号取得(産業組織心理学)。Northwestern UniversityおよびGeorgia Institute of Technologyで博士研究員(ポスドク)をつとめた後、シカゴにあるRoosevelt Universityで教鞭を執る。2017年9月から現職。専門はリーダーシップとチームワーク研究。
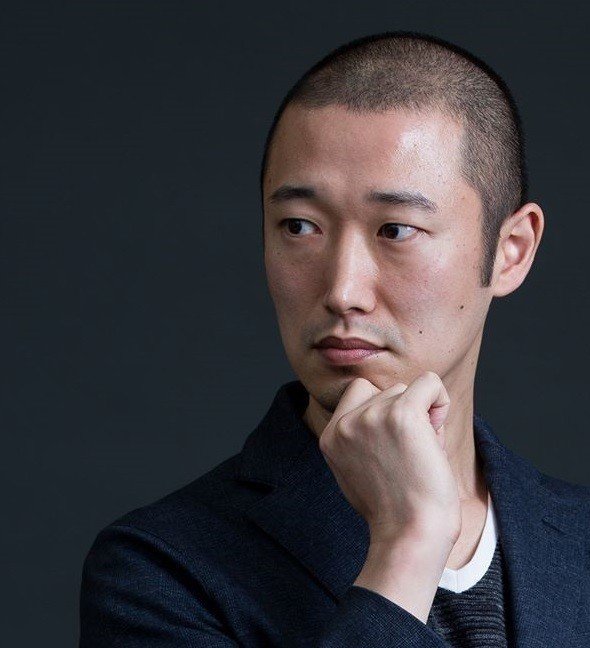
連載:チームで新しい発想は生まれるか
新しいものを生みだすことを誰もが求められる時代。個人ではなくチームでクリエイティビティを発揮するには何が必要なのか? 凡庸なチームと創造的なチームはどう違うのか? 多様な意見やアイデアを価値に変えるための原則はなにか? チームワークのメカニズムを日米で10年以上にわたり研究してきた著者が、チームの創造性に迫る。
第1回:「一人の天才よりチームの方が創造性は高い」と、わたしが信じる理由
第2回:なぜピクサーは「チームで創造性」を生みだせるのか?
第3回:失敗から学ぶチームはいかにつくられるか
第4回:チームの溝を越える「2つの信頼」とは?
第5回:「新しいアイデア」はなぜ拒絶されるのか?
第6回:問題。全米に散らばる10の風船を見つけよ。賞金4万ドル
第7回:「コネ」の科学
第8回:新結合は「思いやり」から生まれる
第9回:トランザクティブ・メモリー・システムとは何か
番外編:研究、研究、ときどき本
第10回:あなたのイノベーションの支援者は誰か
第11回:コア・エッジ理論で、アイデアに「正当性」を与える
第12回:仕事のつながり、心のつながり
第13回:なぜある人は失敗に押しつぶされ、別の誰かは耐え抜けるのだろう。
英治出版オンラインでは、記事の書き手と読み手が深く交流し、学び合うイベントを定期開催しています。連載記事やイベントの新着情報は、英治出版オンラインのnote、Facebookで発信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。村瀬俊朗さんの連載マガジンのフォローはこちらから。(編集部より)

