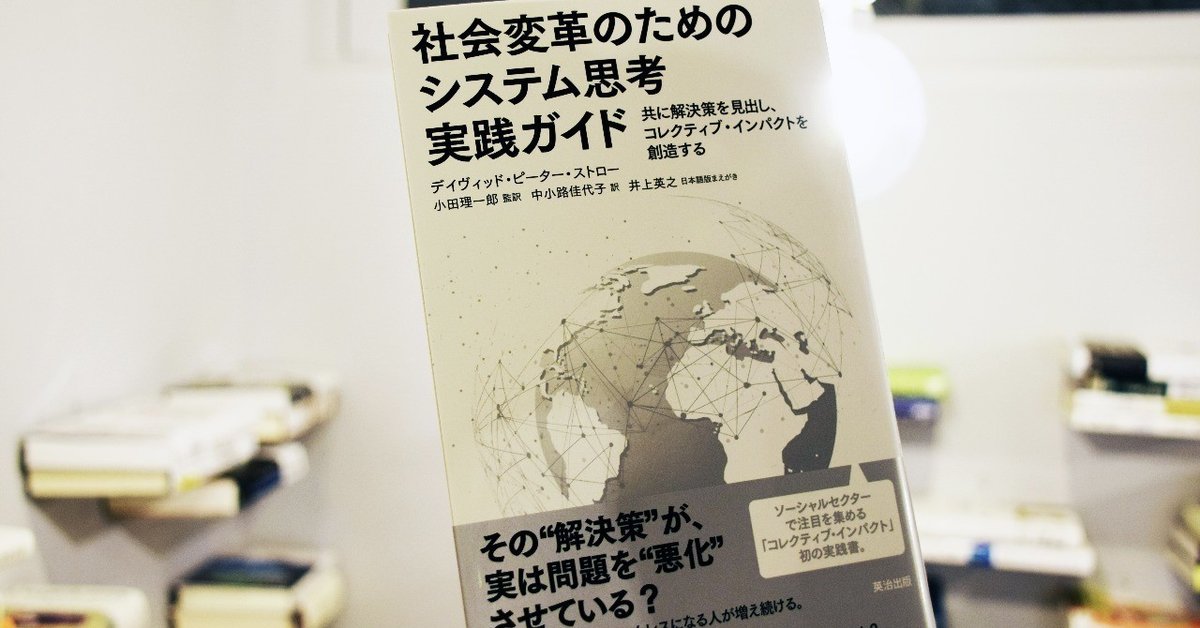
『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』の監訳者による解説を全文公開します。(EIJI Books)
●EIJI Booksとは?
英治出版の本にまつわる読み物を紹介するコーナーです。話題書の著者や編集者へのインタビュー、新刊の本文一部公開、著者と有識者との対談などを通して、「いい本とのいい出合い」を増やしたいと思っています。
●『社会変革のためのシステム思考実践ガイド——共に解決策を見出し、コレクティブ・インパクトを創造する』とは?(2018年11月発売)
一つの組織ではなく、幅広いコラボレーションによって社会全体で問題解決を目指す「コレクティブ・インパクト」という手法が、いま注目を集めています。ここ数年、関連するイベントや取り組みが急速に増え、2018年の政府の「骨太の方針」にも盛り込まれました。
そして本書は、アメリカで20年以上にわたってシステム思考を使った社会変革に取り組んだ著者が、豊富な事例と知見をもとに実践的なプロセスを紹介。まさに「コレクティブ・インパクトの実践書」と言える一冊です。
●12/13(木)出版記念セミナーのお知らせ
なぜコレクティブ・インパクトにシステム思考が必要なのか〜
登壇者:小田理一郎さん、井上英之さん、本木恵介さん
『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』出版記念セミナー、参加者募集中! イベントの詳細・申込はこちらから。
<「監訳者による解説」の見出し>
システム思考の実践と研究
社会変革とシステム思考
コレクティブ・インパクト
社会価値創出に貢献するビジネスの役割
コレクティブ・インパクトの実践に向けて
システム全体から関係者を招集する
多様な参加者の対話のファシリテーション
システム的に考える実践上の一〇のコツ
❶ 課題は、焦点を絞る問いの形で設定する
❷ システム図に取りかかる前に、時系列変化パターングラフを用意する
❸ 「正しい」図を描こうとするのではなく、「役に立つ」図を描く
❹ 関係者たちで一緒に描くだけではなく、一緒に俯瞰して振り返る
❺ 構造のツボを見出す「公式」や「魔法の杖」はない
❻ 打ち手に詰まるときには「クライアント」の範囲を広げる
❼ 洞察からプロトタイプをつくり、新しいシステムの挙動をすばやく見出す
❽ 継続的な学習の文化と能力を育む
❾ 他のシステムに施策を広げる際には文脈の違いに注意する
❿ システム思考家としての「心のあり方」を磨く
今後注目される変化の理論
よりよい未来に向けて
『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』
監訳者による解説(小田理一郎:チェンジ・エージェント代表取締役、『「学習する組織」入門』著者)
●システム思考の実践と研究
私が本書の著者デイヴィッド・ストローと、彼の相棒であるマイケル・グッドマンの二人に出会ったのは、〈組織学習協会(SoL)〉コミュニティの会議でのことでした。彼らは私にとって、システム・ダイナミクス学派の兄弟子です。二人は後輩やシステム思考の初学者に対してとても面倒見が良く、真摯な態度で、難しい質問にも思慮深く、そして愛情をもって答えてくれます。社会や自然に対して共感と愛情を抱き、他者に対しては信頼を基本として接している人物たちであると尊敬の念を抱いていました。
この二人の貢献の中でも著名なのは、本書でも中心に取り上げられている「システム原型」のビジネス分野への応用です。システム原型とは、さまざまな分野で共通して現れることの多い、問題の構造の基本となる型です。もともと、環境・開発分野で数多くの功績を上げたドネラ・メドウズが、一般の市民にもシステムの構造を理解してもらうために発案しました。このシステム原型が示す有用な知恵の一つは、その汎用性です。セクターや業界や規模にかかわらず、現実の問題をシステムのフィードバック構造に落とし込むことができれば、根本原因の掘り下げや解決のためにとるべきアプローチの手がかりを得られるのです。
デイヴィッドとマイケルがこの考え方をビジネスや職場の場面に応用し、実践を積みながら練り上げていきました。彼らのこの貢献は、一九九〇年に出版されたピーター・センゲの『The Fifth Discipline(邦題:学習する組織)』の中で大きく取り上げられています。システム原型を用いることで、難易度が比較的高い作業が多かったシステム思考の実践を、身近な職場やビジネスの問題へ適用することがしやすくなったのです。このシリーズの書籍の発行部数は全世界で三〇〇万部以上にものぼり、世界各国の組織や地域で「学習する組織」の考え方が広がっています。

●社会変革とシステム思考
学習する組織とシステム思考の広がりは、ビジネス分野だけにとどまりません。行政セクター、市民セクター、社会起業家たちの間でもその実践が広がっていきました。本書は、社会変革(ソーシャルイノベーション)と呼ばれる分野において、システム思考および関連する手法が、どのようにして社会変革の効果的な触媒として活用し得るかを示すために書かれました。
社会変革の目指すところは、重大な社会問題に対して、十分に大きなプラスの変化をもたらすことです。この変化を「インパクト」ないし「ソーシャルインパクト」とも呼びます。ソーシャルインパクトとは、「組織あるいはプログラムによる介入がもたらした、広範で長期的な受益者にとっての追加的な成果であり、意図したものも意図しなかったものも、あるいはプラスの変化もマイナスの変化も含んだ正味の変化」と定義されます。
例えば、若者への就業支援、省エネの推進、食品ロスの削減運動、低栄養によって発育阻害のおそれのある子供たちへの食事提供、日本向け商品の生産段階における児童労働撲滅など、さまざまなプログラムによって、対象とする受益者や周辺の利害関係者たちに、さまざまなプラスとマイナスの影響が生ずることでしょう。
望ましい未来を実現するために、実に多くの利害関係者や似たテーマの社会課題に取り組むプレイヤーが関わります。一つの組織が単独で成果を出すケースもありますが、多くの場合は、数多くの組織の活動の集合体として成果が現れます。こうした成果は、自組織がモノやサービスを産出しても他の組織の成果達成の前提条件を満たさないこともあるし、むしろ他組織の活動が意図せずに自組織の成果を阻害する場合もあるでしょう。また、似たテーマに取り組むプレイヤーたちが、限られた資金や人材を奪い合うことも考えられます。
社会変革の取り組みは高度な複雑性が特徴です。まず、あるテーマの社会問題に対して、さまざまな個人やグループ、コミュニティが関わっており、それぞれの文脈が違う場合が多いという意味の複雑さです(詳細の複雑性)。
そして、短期的な成果を出す施策は長期的にはマイナスの成果をもたらし、逆に長期的に成果を出す施策は短期的にはマイナスの成果をもたらすことがしばしばあります(ダイナミックな複雑性)。
また、同じテーマの社会問題に関わる人たちの間でも、現状はどのようになっているのか、何が問題なのか、何がその原因か、何が目指す姿か、何が解決策か、どのような資源配分や順序立てがなされるべきかなど、さまざまな点で、違った認識や意見を持っていることは当たり前のようにあります(社会的な複雑性)。
さらに、仮に「正しい解決策」があったとしても、それを誰が、どのように伝えるかによって効果が異なり、しばしば介入者自身の態度や行動が「システムの抵抗」と呼ばれる逆効果を生み出すこともあります(適応を要する課題)。
●コレクティブ・インパクト
このような文脈の中で、井上英之さんの「まえがき」および本書第2章で示された、「コレクティブ・インパクト」への注目が高まります。コレクティブ・インパクトは、「異なるセクターから集まった重要なプレイヤーたちのグループが、特定の複雑な社会課題の解決のために、共通のアジェンダに対して行うコミットメント」を指します。コレクティブ・インパクトを進めるうえで必要となる重要な要素は「共通のアジェンダ」「共通の測定方法」「相互に補強し合う活動」「継続的なコミュニケーション」「バックボーン組織」です。
本書の第1部では、コレクティブ・インパクトを実現するための大きな二つの要素として、「システム全体から関係者たちを招集すること」と、「システム的に考えること」を提唱したうえで、後者のシステム的に考えることに必要なシステム思考の基礎を紐解いています。
第2部では、具体的にシステム全体から招集された関係者たちによって進める一連のプロセスとして「4段階の変革プロセス」が紹介されています。
第3部では、社会変革の実務面からの補足として、「変化の理論」「評価」「システム思考家の心得」という三つのテーマが紹介されます。
「変化の理論」は、関係者たちによる「共通のアジェンダ」を構築し、また「相互に補強し合う活動」の青写真となります。
組織・プログラムのインパクトの評価体系は、関係者たちに「共通の測定方法」を設定すると共に、社会全般および主要な関係者たちに成果を的確に伝え、関係者たちの学習を促すための「継続的なコミュニケーション」の基盤となります。バックボーン組織は、こうした多様な関係者たちの活動をコーディネートするうえで重要な役割を担う組織です。
最後に、ファシリテーターや社会起業家に欠かせないリーダーシップ資質としてシステム思考家(システムシンカー)としての「あり方」を培うことを奨めています。
まさに、コレクティブ・インパクトを進めるためのエッセンスが凝縮された一冊と言えるでしょう。
そして、たとえあなたやあなたの組織が、他の利害関係者とあまり関わっていない場合でも、本書のプロセスは大いに役立つでしょう。組織内で理念、戦略、中長期計画を策定する際、新しいプログラムの立案する際、あるいは節目を終えて評価を行う際などに活用できるでしょう。そして、組織内の経営陣、スタッフ、理事会の中で、あるいはさらに広げて、資金提供者やサポーター、ボランティア、そして受益者などの関係者を呼び集める機会があれば、共にシステム的に考えることの価値を実感できることでしょう。
●社会価値創出に貢献するビジネスの役割
これまでは公的機関や非営利組織が社会変革を主に担ってきましたが、企業などの民間セクターにも期待が高まっています。グローバル化や経済開発の陰で、環境の破壊、温暖化問題、社会コミュニティの崩壊など、企業はともすると社会問題を生み出す原因であるという見方が、社会・環境問題の活動家の間には根強くありました。しかし、ここ二〇年ほどで機運は変わり、「企業は社会問題の解決に携わる重要な利害関係者である」との見方が生まれ、期待が寄せられているのです。
そうした背景もあって、企業の評価において「ESG」や「CSV(Creating Shared Value)」などのキーワードが注目されています。ESGとは、環境(Environment)、社会(Society)、ガバナンス(Governance)の三つの側面から見た企業のパフォーマンス評価であり、世界的な投資対象基準として採用され、近年日本でも、とくに企業評価の分野で注目されています。またCSVとは、政府・市民セクターと協働し、社会価値と事業価値の双方を創出する活動のことを指します。企業の立場からも、新たなビジネスの創出を見据えて、社会問題へ関心を寄せるようになっています。
日本では、以前から「三方よし」「論語と算盤」と言われるように、社会道徳を前提にした経済を志向する考え方がありました。社会的な活動を単なるかけ声倒れに終わらせずに、企業理念と合致した現実の変化を創り出すうえでも、この社会価値創出についての実践的なアプローチが求められるところです。
* 三方よし:近江商人が「商の菩薩道」を提唱したことに始まり、1970年代にその思想を紐解いて「買い手よし、売り手よし、世間よし」の三方にとって価値を生み出すことの重要性を説くにいたった。
論語と算盤:渋澤英一の著書にあるように、商売の基本には道徳倫理が必要であるとする商業理念。
実際、海外では、環境問題や社会問題に対する社会変革を他のセクターと連携することで、新規事業を創出し、企業の評判を高め、財務的にも優れた成果を残す企業がたくさん現れています。それらの社会変革に成功する企業では、担当者たちが、本書にあるような実績のある手法とプロセスを用いていることも見逃せないポイントです。
●コレクティブ・インパクトの実践に向けて
このような背景の中で、デイヴィッド・ストローのこの著書は極めてタイムリーだと言えるでしょう。「VUCA(脆弱、不確実、複雑、あいまい)」時代と言われる今日、システムそのものの変容とそのためのシステム横断のコラボレーションが、ますます求められるようになっています。しかし、システム横断のコラボレーションは、「言うは易し、行うは難し」の最たるものです。十分な関係者たちの意志と、個人および集団としての能力が備わらなければ為し得ません。事実、コラボレーションの失敗のほとんどは、招集時点あるいは変化の基盤づくりの段階で起こります。
本書は、コレクティブ・インパクトあるいはシステム横断のコラボレーションの構築を念頭に、システム思考だけでなく、「学習する組織」他の四つのディシプリン(「メンタル・モデル」「チーム学習」「自己マスタリー」「共有ビジョン」)を統合したプロセスを紹介しています。実務上のプロセスの経験を積んだ方や学習する組織の方法論に通じた方にとっては、本書は過不足なく情報を提供してくれています。一方、なじみの薄い方にとって、実際にどのように始めるのか疑問が残る方もいらっしゃるでしょう。
以下、この解説では、システム全体から招集することと、システム的に考えることのそれぞれについて、実務的なプロセスを紹介します。また、最近国際的に公的資金や助成金を得る際に求められる変化の理論について、本書と実務の関連を紹介します。
システム全体から関係者を招集する
本書の事例では、デイヴィッドたちはファシリテーターとして呼ばれており、招集者が別にいることが多いようです。招集段階について世界各地で成功と失敗の双方の経験がもっとも豊富なファシリテーターは、カナダ人のアダム・カヘン氏です。南アフリカやコロンビアで多様な利害関係者たちのコラボレーションをファシリテーションし、それぞれマンデラ大統領、サントス大統領のノーベル平和賞受賞に貢献しました。彼の著書『社会変革のシナリオ・プランニング』と『敵とのコラボレーション』では、このシステム全体から関係者を招集することに関して具体例と共に描いています。ここではその要点を紹介します。

まず、会合そのものの参加者を決める招集チームを結成します。さまざまなセクターから関係者たちを呼び集めるには、各方面にネットワークをもち影響力をもつキーパーソンたちが必要となります。ファシリテーターを含めて3〜7名程度で構成されるこのチームが、関係者の人選を進め、参加を呼びかける役割を担います。参加者を決める際には、地域システムや社会システムを代表する小宇宙を形成することを目指します。各セクターや業界の有力なリーダーを含めることが多いですが、本書にあるように声なき多くの一般市民や受益者を代表できる人や、全く異なる視点を提供できる人を含めることが大切です。
理想的には、数ヶ月~二年間にわたって、合計で一〇日~二〇日のプロセスを設計することが望ましいでしょう。南アフリカの事例では、忙しすぎる各党の代表ではなく右腕となっている中堅若手を集めたことで、その後の国づくりの人材育成の場にもなりました。物理的にそれだけの日数の参加がかなわない場合には、さまざまな視点や声を集めるために、参加者たちが現地を訪問する、会場へゲストスピーカーとして知見を共有してもらう、インタビューするなど、さまざまな方法を組み合わせることが出来ます。いわゆるアンケートや、複数人同時にインタビューするフォーカスグループなどの情報も役立つでしょう。
ただし気をつけておきたいのは、統計とプロファイリングによって過度に抽象化すると、人間性やリアル感がどうしても失われがちですので、実在する人物に関する記録や証言あるいはストーリーとして提示するのがよいでしょう。
また、「全体から関係者を集めたい」とする招集者の意図を一方的に押しつけるのは逆効果です。アダム・カヘンは『敵とのコラボレーション』の中で、協働は必ずしも最善の選択肢ではない、として、参加者の立場からどのような選択肢があるかについて解説しています。本書でデイヴィッドが記述することと重なりますが、協働以外にも、「対立」「適応」「離脱」の選択肢があり、これらと意識的な比較を行ったうえで、参加者自らが選択するように働きかける姿勢を持つことも大切です。
多様な参加者の対話のファシリテーション
さて、多様な関係者たちが集まったところでどのように話し合いを進めればよいでしょうか。共通の社会課題のもとに集まったとしても、その役割、目的、方針、立ち位置、信念や価値観には大きな違いがあることは珍しくありません。そのような人々が生産的な会話を行うためには、力強く安全な「器」が欠かせません(本書では第3章で簡単に言及されています)。
器とは、日本でいうところの「場」の概念と類似していますが、さらに踏み込んで囲いや蓋がしっかりあることが特徴です。囲いの例として、物理的に日常と違う場所で開催することや一連の会合の期限を決めておくことのほか、このプロセスに参加する全員が、組織内外の批判や攻撃から守られるような手立てを打つことが含まれます。また囲われた場に蓋があることで、器の中でエネルギーや感情が発散され、ぶつかり、やがて気圧(プレッシャー)が高まる中で調和していく一つの大きな流れが形成されるように器を保持できる機能が形成されます。
この安全な器の中で、参加者間の意見、感情、エネルギーが相互に交わされるプロセスを設計し、遂行するのがファシリテーターの重要な役目であり、そのために必要な学習する組織のディシプリンが「チーム学習」です。本書では、チーム学習の基盤となるメンタル・モデルと対処法としての「推論のはしご」および「主張と探求のバランス」が紹介されていますが、これは参加者一人ひとりが理解して身につけられるような学習の場を設けると効果的です。
チーム学習を進めるうえで重要なフレームワークとして、オットー・シャーマーの発案した四つの話し方・聴き方(聞き方)がとりわけ役に立つでしょう(図1)。

最初の会合では、よそよそしく丁寧に話したり、場合によっては互いに警戒したりするかもしれません。また、主催者チームや有力者が一方的に話すばかりで、それ以外の人があまり話せないような状況も起こりがちでしょう。このレベル1の状態を「儀礼的な会話(ダウンローディング)」と呼び、丁寧さや恐れに満ちた話し方となり、自分の経験と照らし合わせて過去のパターンに沿うかどうかを考えながら会話する予測的な聞き方になります。この状態では、既存のシステム構造を反映するだけで、変容は何も起こりません。
ファシリテーターが心がけるのは、まずそれぞれシステムの部分を構成する人やグループが、それぞれの考えをはっきりと述べるような状態にすることです。立場によって異なる意見が出され、意見の相違や衝突がはっきりしてくると、レベル2の「討論(ディベート)」の状態になります。ここでは、意見が衝突する話し方となり、どの意見が妥当か判断しようとする聞き方が中心になります。
さらに、異なる意見をもつ他者に対して共感的な聴き方をし、そして、システムの中で自身の知らないことや問題へ加担しているかもしれないことに対して内省的な話し方が組み合わさると、レベル3の「内省的な対話(ダイアログ)」と呼ぶ状態に場がシフトします。未来に向けての方向転換が始まるときでもあります。
そこからさらに俯瞰が進み、自他を分けていた境界を越えて、そこにいる人たちが分かたれない一つの全体であると悟る境界のない聴き方と、場から生まれる叡智に委ねる生成的な話し方ができるようになると、レベル4の「共創的な対話(プレゼンシング)」と呼ばれる状態に場がシフトします。
ファシリテーターは、このような場のシフトを意図することはできますが、実際に場を構成するのは参加者たちです。参加者たちが、自分たちで場のシフトを進めていくために、ファシリテーターは対話のグラウンドルールを定め、メンタル・モデルを保留すること、視座を転換すること、目的にそぐわないメンタル・モデルを手放し、出現しつつある未来を形にすることを推奨し、場が動くのを待ちます。
実は、本書で書かれているシステム思考の世界観およびプロセス自体が、こうした場のシフトを支援してくれます。
システムに関するストーリー、時系列変化パターングラフ(後述)、システム図の変数出しなど、それぞれの立場から見えやすいシステムの構成要素や側面を出し合うことで、それぞれが意見を述べて場に貢献する機会を作ります(レベル1→2)。また、変数が別の変数に対してどちらの方向に影響を与えるのか、どんな仕組みなのかについて、正しさの判断は保留してさまざまな意見を一つの平面上に書き込んでいきます(レベル2)。
システム思考の重要な原則は、構造が挙動を作り出すことです。従って、責任者や担当者が代わっても繰り返し起こる問題や挙動に対して、人を責めるのではなく、どのような構造がその挙動につながるかを考えます。具体的には、人が置かれた物理的および人的な環境、意思決定をする際に入手できる情報、目に見える目標・ルール・インセンティブ・罰則などです。システム図の中でもっとも重要な着眼点の一つは、関係者の認知や行動にあります。
ある特定のプレイヤーが認知・行動する際に置かれた文脈に身を置いてみることで、相手の立場に立ち、同意はしなくとも行動や発言の背景や理由を理解し、共感することがしやすくなります。さらには、自分自身の置かれた環境が全体から切り離されていたり、あるいは、自身の行動が意図せぬ結果をもたらしたりしていることもあるでしょう。また、他者と対峙するのではなく、隣り合ってシステム図を眺めることも、相手や自分を責めるのではなく構造を客観的に見やすくする構図をつくります(レベル3)。
そして最後に、固定観念の枠組みを超えて、より広い視野で全体像を捉えたシステム図を俯瞰することで、いかに互いがつながっているか、それぞれが全体の一部になっているかを見えやすくすることができます。一人ひとりが全体の俯瞰図の作成に関わり、オーナーシップを持って話をしたならば、共創的な対話は起こりやすくなるでしょう(レベル4)。
ピーター・センゲは、システム思考と対話(チーム学習)はあざなえる縄のようなものだと言います。システム思考は、システム全体から招集された関係者たちの対話を助けます。同時に、より開かれた深遠な対話は、システムの深い理解、共感と内省、新たな意図とビジョンの生成を助けるのです。
しかし、システム思考のプロセスが、対話を助けやすい構造になっている一方で、それだけでは場のシフトが起こるとは限りません。システム思考を実践する者はチーム学習のディシプリンにも通じることでその大きな相乗効果を生み出しやすくなります。個人として両方を使いこなすことが難しい場合、システム思考に強い人と対話ファシリテーションに長けた人とチームを作り、ファシリテーションするのもよいでしょう。
システム的に考える実践上の一〇のコツ
システム思考は、「なぜシステムはその挙動を示すのか」、そのシステムの構造を理解し、また「システムの挙動を望ましいものにするために、どのように構造へ介入すればよいか」について探求するプロセスです。
本書では第3章、第4章でその基本を紹介し、また、第2部において、社会システムを代表する関係者たちとどのようにシステム的に考えていくかというプロセスについて説明しています。これから、関係者たちと共同でシステム的に考えるための実践上の一〇のポイントをご紹介します。
なお、システム思考の実践プロセスについてより詳細に関心のある方には、初学者であれば『なぜあの人の解決策はうまくいくのか』あるいは『「学習する組織」入門』、より深く学ぶにはジョン・スターマン著『システム思考』をお勧めします。
❶ 課題は、焦点を絞る問いの形で設定する
システム思考と言えば、「木だけでなく森も見る」と表現されるように、全体像を理解しようとします。教育問題、環境問題、貧困問題、少子高齢化問題、過疎問題など、漠然とテーマだけを掲げ、たくさんの変数を書き出し、また、その変数間の因果関係をつなごうとすると、散々議論したあげくにスパゲッティのような図ができあがります。しかし、解決策を導き出すうえで「スパゲッティ図」はほとんど役に立ちません。
ループ図を描く前に、必ずシステム図を描こうとする目的、システム的に考えようとしている課題を明らかにします。課題とは、達成したい目的・目標や解決したい問題に関する重要な論点であり、さらに、答えを見いだすことによって大きな前進が期待できるような「問い」のことを指します。
本書では、「焦点を絞る問い」として紹介されていますが、「なぜ善意にもかかわらず、目標が達成されていないか」「なぜ努力にもかかわらず、結果が出ていないのか」といった、「なぜ」を深掘りする問いは有効です。
また、本書では示されていませんが、期限をつけた目標レベルを設定するのも有効です。「いかにして三年以内に全ての児童・生徒が自主的に学ぶ文化を築くか?」「いかにして二〇三〇年までにA市で発生する温室効果ガス排出量を三〇%削減するか?」「いかにして一〇年以内に人口の減少を反転させるか?」など、具体的な目標設定と時間軸があることによって、システムの中で見るべきポイントが明確に浮き上がってきます。
課題の設定は,大海原で海底にアンカーを打ち込むような役割をします。システム図を描くときに思考が拡散してどんどん範囲が広がっていったときに、課題に照らし合わせてそうした変数やつながりを考えるのが妥当かどうか、問い直すようにしましょう。もし課題の問いから横道にそれていたら、アンカーのあるところへ戻ります。しかし、もし多くの人が、そもそも課題の設定が違っていたと理解したならば、課題を書き直し、新しいアンカーを打ち直してもよいでしょう。
❷ システム図に取りかかる前に、時系列変化パターングラフを用意する
システム図を描くプロセスは、課題として設定した問いへの答えを導くためですが、できあがったものを見ても、抽象的な表現に留まっているのではないかと思われるかもしれません。具体的にシステム図は何を説明するのか、あるいは、どこまで描けば十分描けたことになるのでしょうか?
もしシステム原型のテンプレートに当てはめるレベルを超えて、ループ図、ストック&フロー図やシミュレーションモデルを築く場合、実践家が必ず行うことは「時系列変化パターングラフ」を描くことです。時系列変化パターングラフは、横軸には十分遡った過去から目標を達成したいと考える未来までの時間軸を設定し、縦軸にはシステムの重要な指標を設定して、折れ線グラフを描きます。システムの重要な指標とは、目標として達成したい短期・中期・長期の成果、組織の活動への投入・活動・産出の量や質などです。過去から現在は今まで実際に起こったパターンを、未来に関してはなりゆきパターンに望ましいパターンを加えるなど、複数のシナリオで描くとよいでしょう。
私たちは、投入、活動、産出、成果、インパクトの間で多少のリードタイムの遅れがあっても線形に進むとイメージしがちです。しかし、現実のシステムはもっと複雑で線形ではないことがしばしばです。例えば図2の右側のグラフのように、実際にパターンを描いてみると、短期的には投入に対してプラスの成果を示しても、ある時点からマイナスの成果を示している、という洞察を得られることもあります。

財務や生産などデータが存在する指標ではデータを活用する一方で、データが一部しかなかったり、まったく存在しない指標では参加者の主観的な評価を集めてそのバラツキや差異について話し合ってみてもよいでしょう。「動機付け」や「帰属意識」など定性的な指標であっても、参加者が重要だと考えていることはグラフにしましょう。多様な関係者が集まっている場合では、それぞれの人が気になる指標についてグラフを描いてストーリーを語ってもよいでしょう。グラフの動きに緩急の変化があるときや反転するときに何が起こっているか、平時だけでは見えないさまざまなシステムのストーリーが現れてくるでしょう。
ドネラ・メドウズ曰く、「システムのビートを白日のもとにさらす」のです。システム図が完成したかの目安は、時系列変化パターングラフに描かれた「今まで」のパターンと「なりゆき」のパターンを説明できているかどうかを基準にします。もし自己強化型ループやバランス型ループ、インフローとアウトフローの組み合わせが、パターンに現れる動態を説明しきっていればそれ以上無理に広げる必要はありません。
❸ 「正しい」図を描こうとするのではなく、「役に立つ」図を描く
先ほどシステム図完成の目安を述べましたが、そこに描かれた変数やそのつながり、あるいはループに関して、本当に正しいのかと悩むこともあるでしょう。もちろん妥当性や根拠は必要です。工場の生産システムの問題やビジネス向けの部品設計など、比較的閉じられた、複雑性や不確実性の少ないシステムでは、「正しい答え」も存在するでしょう。そうした課題については、モデルを定量化し、統計的な分析などを加えて、過去のパターンを十分に再現し、堅牢性の高いモデルを築くことができるかもしれません。
しかし、社会システムの複雑な課題においては、「正しさ」や「正解」にこだわりすぎることによって、課題解決がかえって難しくなることもありえます。そもそも、描き出されたモデルは、世の中をある視点から単純化したものに過ぎません。統計学の大家ジョージ・ボックスは、「すべてのモデルは間違っている。一部のモデルは役に立つ」という格言を残しました。
意見の食い違いが見られるときには、それぞれ自分が正しいと主張する人たちがいたとしましょう。システムではどちらも正しい可能性があり、それでも、自分以外の意見を間違いだと言い張る場合には、部分しか見てない可能性があります。その大きな理由の一つは、何が正しいかについては、そのシステムの境界と目的をどのように定義するかによって異なるからです。何かを「正しい」と主張する際、その背景には正しさの判断基準となる目的、前提、境界が存在します。さまざまな価値観を持つ人たちで構成された社会の中では、それぞれが見ている立場によって目的、前提、境界が異なり、さらに何が望ましい行動かを判断するにあたっての価値観や基準が異なるものです。このような違いに無自覚のまま自分の主張や解決策にこだわってしまうと、せっかくの協働の機会を逃してしまうことにもなりかねません。
「正しいか」ではなく、「役立つか」という視点でモデル化に取り組めば、気づきや洞察、新たな問いが生まれやすくなります。そして、人々が自分たちの前提を振り返り、目的達成に向けて今までにはない探求や思考実験を行いだしたら、それは「役立っている」ことの証左です。
そのため、本書でも強調されているように、できるだけ異なった視点や意見を持つ人たちを集めることが重要になります。システム図を描き始める初期段階では、できるだけ多くの変数や因果関係の仮説を出せたほうが後々役立ちます。このとき、その変数は関係ない、その因果関係は間違っているといった議論にならないように注意しましょう。できるだけさまざまな見方を仮説として受け容れて、それを俯瞰しながらどのループや経路のダイナミクスが支配的かを、過去、現在、未来などいくつかのフェーズに分けて整理することで、役に立つ洞察が現れやすくなります。
また、それでもより整ったシステム図がほしいという場合には、システム思考の専門知識をもった人たちに後日整理を任せることにしてもよいでしょう。
❹ 関係者たちで一緒に描くだけではなく、一緒に俯瞰して振り返る
システム図を描き上げたら、すぐに解決策を見出す議論に進みたいという誘惑に駆られるかもしれません。それでも一度立ち止まって、作成したシステム図を参加者全員で俯瞰して、内省・対話をする時間を設けるのが有意義です。そして、本質的な洞察や問いをできるだけ多く出しましょう。利害関係者が集まる時間が限られているのであれば、持ち時間をシステム図作成だけに使い切ることはせず、ある程度描いた段階で振り返りの時間を設けるとよいでしょう。
うまく描けていてもいなくても、できあがったシステム図はそこに集まった関係者たちのメンタル・モデルを反映したものです。出てきた変数や関係性には偏りがないでしょうか? 見逃している領域はないでしょうか? もしかしたら、その段階で初めてその場に招集すべきだった関係者の存在に気づくこともあるかもしれません。
システム図のもっとも有用なポイントは、その中にいる当事者がどのような環境下にあるために、ある意思決定や行動をとり続けるのか、という洞察を得ることです。情報フィードバックの欠如、遅れ、ゆがみなど、システム図の中にその洞察がすでに現れているかもしれませんし、あるいは、行動をとる当事者の内面のメンタル・モデルに由来することもあるでしょう。他者の立場で共感的にシステム図をたどると共に、自分自身の行動にも目を向けましょう。
❺ 構造のツボ(レバレッジ・ポイント)を見出す「公式」や「魔法の杖」はない
小さなリソースで大きな成果を得やすい場所、すなわち「構造のツボ」とはなんとも魅力的な概念です。しかし、システム図が描けたからといって、何が構造のツボであるかを導出する方程式があるわけではありません。また、仮に見つけたとしても、システム・ダイナミクスの創始者ジェイ・フォレスター曰く、ほとんどの人は、構造のツボを反対の方向に押してしまうこともしばしばあるそうです。
システム思考の先達たちが言うには、結局問題に取りかかる当事者たちが、一緒に頭に汗をかいて、探求し、見出していくものだということですちょっとがっかりする方もいらっしゃるかもしれませんが、重要な洞察を得るための近道はないのです。
しかしながら、どのように探求すればよいか、先人たちが残したヒントも存在します。
構造のツボの探し方について、特にシステム原型の罠にはまっている場合の抜け出し方は詳細に本書に書かれています。それ以外にも要点をついた説明がありますが、もっと学びたいという方には「レバレッジ・ポイントを見出す場所」について記した、ドネラ・メドウズ著『世界はシステムで動く』第6章を参考にすることをお勧めします。メドウズは、構造のツボを探す一二の手がかりを示しています。

「レバレッジ」というと、物理的な「てこの作用」や、財務上のレバレッジなどを思い浮かべるかもしれませんが、システム思考、とりわけ社会問題におけるレバレッジのほとんどは、つながり、波及、循環、蓄積など、要素同士の作用です。具体的に構造のツボを探る際は、今まで行われているどんな働きかけが、システムが機能するためのさまざまな条件を損ない、関係者たちの力を奪っているのか、逆にどんな働きかけが、システムが成果を発揮するための最適な条件を整え、関係者たちを力づけているのかを探求します。
また、複雑な社会課題においては、どれか一つだけの要素や構造のツボに働きかけるだけではうまくいきません。全体的に良い循環が生まれるような、複数の働きかけをデザインしていくことが大切です。さらに、それらの中で優先順位付けを行うのではなく、どのような順序(短期、中期、長期など)で行うべきかを検討します。

❻ 打ち手に詰まるときには「クライアント」の範囲を広げる
システム図の描き始めに変数を列挙するとき、どれくらいの粒度で出せばよいか、という疑問がよく生まれます。全体的には、一般的な要因分析に比べてやや粗めに始め、セグメント分け、種類分けは最低限にします。あえて種類分けを行うのは挙動の動態が違う時に限定します。
ここで基準となるのが「クライアントの範囲」の考え方です。クライアントとは、システム図のユーザーであり、一緒にその社会課題に取り組もうとする「私たち」と言えるグループの範囲です。自身、自部署、自組織だけがクライアントになることもあれば、部署横断、組織横断、あるいはセクター横断のチームがクライアントとなる場合もあるでしょう。
クライアントにとって「内因性」の問題、つまりクライアント自身が打ち手を講じることができる範囲の問題であれば、変数の粒度はある程度細かくてもよいでしょう。一方で「外因性」の問題、つまりクライアント以外の他者の挙動に左右される範囲では、クライアントがとるべき打ち手が探せないため、細かい粒度の変数を設定することはあまり意味がありません。
また、有効な打ち手が見つからない場合もあるでしょう。そのようなときは、クライアントの範囲を広げるのも一手です。大きなシステム構造を目のあたりにして、自分だけ、自部署だけで無力ではないかと感じる場合、他の人や他部署を巻き込んでいくと、打ち手の幅が広がります。社会問題に取り組むときにはなおさら、一つの組織単独での影響力や打ち手の幅は限られやすいものとなります。だからこそ、コレクティブ・インパクトを目指して、組織横断・セクター横断で取り組む意義が大きいのです。
❼ 洞察からプロトタイプをつくり、新しいシステムの挙動をすばやく見出す
多様な関係者を集めてシステム分析を行い、構造のツボを見出すだけで、うまくいく打ち手は講じられるのでしょうか? 既存のシステムを大きく変えるのではなく、継続的に改善していこうとするならば、システム分析だけでも改善につながることが多くあるでしょう。
しかし、複雑な問題を抱えるシステムにおいて、当初決めた戦略通りにものごとが進む保証はないため、不確実性について考慮する必要があります。特に、新しい領域や地域での取り組みや、イノベーションにつながるような新しい施策を探る際には、多くの関係者たちを集めたとしても、そもそもシステムがどのように変容していくかという知見が限定的にしか得られないことがままあります。
そこで有用なのは、想定外の状況が起こっても適応できるように、どんな行動や結果をモニターしていくかについて取り決め、定期的に振り返りを行って軌道修正を行う「適応マネジメント」の仕組みをあらかじめ組み込んでおくことです。振り返りを行う頻度は、チーム単位であれば数週間ごと、全体では数ヶ月ごとなど、組織やシステムの規模に応じて設定します。
また、革新的な手法を実施するのであれば、想定されるリスクやコストについて引き受けられる範囲の小規模なプロトタイプをつくり実験を行うようにします。こうした実験や進捗のモニタリングが、システムに関しての有用な知見を提供します。
❽ 継続的な学習の文化と能力を育む
システム思考の実践において欠かせないのは「システムそのものの継続的な改善」です。
* システムそのものの継続的な改善:優れたシステム思考家であるエドワーズ・デミングが提唱したトータル・クオリティ・マネジメント(TQM)の根幹の考え方。
振り返りを通じて進捗を確認し、効果をモニタリングしながら、適宜リソースを投入したり、施策を調整したりすることによってシステム全体の改善を図っていきます。この学習プロセスを通じて、システムの構造やその前提に関する新たな知見が得られれば、その知見について探求を深めることは有用です。なぜなら、以前から継続している戦略を見直したり、新たな戦略がうまくいくために必要なことを検討したりするのに役立つからです。とりわけ、顧客や受益者や彼らを取り巻くコミュニティにおいてどのような変化が起きているか、といった「現場の情報」を迅速にフィードバックすることが、迅速な学習サイクルを回すのに欠かせません。
また、説明責任は社会変革を担う組織にとっても重要な要素です。しかし、できるなら「説明責任のための場」と「学習のための場」を切り分けて進めるほうがよいでしょう。学習とは、自分たちに知らないことがある、もっと改善できる余地がある、といった具合に、無知や不完全であることを認めて初めて起こるものです。まして、リソースをとりあう他の組織や、評価する立場の組織の人たちと一緒の場で、深く内省し、今までの当たり前を疑い、新しい発想を生み出すには、安全な場が欠かせません。学習を最大化するために、参加者たちの心身の安全を確保することが協働の招集者の重要な務めとなります。
❾ 他のシステムに施策を広げる際には文脈の違いに注意する
プロトタイピングや新しい施策がうまくいけば、規模の拡大(スケールアップ)や、別の地域に広げる水平的な展開(スケールアウト)を目指す施策へと進むことができるでしょう。
ここで注意したいのは、ある場所でうまくいった施策を、そのままの形で他のコミュニティや地域に適用しようとしていないか吟味することです。実際、多くの社会変革の取り組みがこのパターンで失敗しています。
その理由の一つめは、問題の前提となるボトルネックの組み合わせが異なる場合です。たとえば、ある市場でうまくいった優れた技術や製品があったとしても、別の場所ではそもそも電気へのアクセスや道路・水路などインフラが整っていなかったり、設置された装置のメンテナンスを行える技師や技術的知識がなかったりします。その場合、何の付加価値も生みだせないかもしれません。二つめの理由として、水の問題に見られるように、同じテーマの問題でも場所によって背景や状況が大きく異なる場合もあるでしょう。そして第三の理由として、社会問題の多くは技術的には解決できない「適応を必要とする課題」であることが挙げられます。介入者を含めた関係者たちが、どのように学習し、変化に適応するかが問われるのです。
このような失敗を避けるための処方箋は、現実をありのままに見ることです。また、後述する変化の理論を構築できていれば、そこにはビジョンの実現に必要な、さまざまな前提条件が明示されていますので、そうした前提条件が展開したい場所でどのようになっているかを吟味するのもよいでしょう。
個別のテクニカルな施策を流用する代わりに、本書で示されるような組織学習プロセスをそれぞれの地域に活用することは重要でしょう。人や組織間のコミュニケーションや学習は文化に依存するものの、そのパターン認識も踏まえ、実績ある参画型メソッドを活用することは、結果的にプログラム展開のスピードを速めるであろうと考えます。
❿ システム思考家としての「心のあり方」を磨く
システム思考や組織学習に造詣の深いビル・オブライアンは、システムへの働きかけの成否は、システムに介入する者たちの「心のあり方」に大きく左右されると言いました。一部の権力者や意思決定者が、自らのエゴのみで動いたり、あるいは、関係者たちの受容を促すような関与や包摂(インクルージョン)のプロセスを経ずに進めたりすると、後になって大きなシステムの抵抗を招いたり、あるいはシステムの崩壊を導くことすらあります。自分はエゴにとらわれていないと思っていても、先ほど述べたように「自分がすべてを知っている」と考えてしまうと、落とし穴があったりするものです。システムへの働きかけを通じて社会変革を志すなら、自らが常に学習者であるという姿勢が必要だと考えています。
人の性質は簡単には変わるものではありません。まずシステム思考を実践する者が、自らのあり方を見つめ、継続的に学んでいく必要があります。システム思考家は、人そのものを変えることができなくとも、何を見るか、どのように考えるか、どのような行動がとりうるのかについて新たな可能性を知らせることができます。第13章「システム思考家になる」で述べられていることは、実践者がどのように自らを磨き続けるかの手引きとなることでしょう。
今後注目される変化の理論
近年、多くの基金、財団、資金助成団体などが、プログラム申請の際に「変化の理論」の作成添付を必須条件とするケースが増えてきています。また、ソーシャルインパクトを計測するための指標設計や、インパクトを生み出す際の費用対効果を測るSROI認証などでも変化の理論が求められるようになっています。今後、企業関連の資金や投資資金がソーシャルインパクトを生み出そうとする事業に流れるに従い、このトレンドはますます強まっていくでしょう。
変化の理論とは、社会問題に関わるプログラムの計画、評価、そして利害関係者たちによる参画の方法論です。具体的にはある文脈の中で望ましい変化が、なぜ、どのように起こるかを包括的にわかりやすく描写した理論です(学術的な意味の理論や一般的な法則を示すものではなく、特定の文脈における特定のビジョン実現に向けたプロセスとして現場で共有・実践される理論を指します)。
変化の理論の主体は、しばしば政府、企業や非営利団体などの単体の組織という枠組みを超えて、顧客や受益者を含めた関係者全般となります。それぞれの関係者にとって、どのような条件が整うことで変化が起こるのか、また、その条件を満たすために、それぞれの関係者たちがどのような介入を行うかを明示し、互いの組織やプログラムの関係性を明らかにします。
本書の11章では「成功増幅」と「目標達成」という二つのシステム的な変化の理論が説明されています。詳細については本書を参照にしていただければと思いますが、ひとたび、変化の理論が明らかになれば、それを見せるべき相手によってシステム図の抽象度を調整することが有用です。たとえば意思決定者や一般市民向けには、シンプルに作り直した好循環のモデルのほうがわかりやすいでしょう。また、実務者向けには、より詳細なシステム図のほうが、自分たちがそれぞれの介入で求められるアクションに、どんな文脈や条件があるか、あるいは、どのような状況やKPIをモニターする必要があるのか、などを明らかにしてくれます。
* KPI:鍵となるパフォーマンス指標
(Key Performance Indicator)のこと。
ちなみに、本書で紹介するシステム的な変化の理論以外に、さまざまな形の変化の理論が運用で用いられています。英語で「Theory of Change」と検索をしてみると、実にさまざまな解釈や運用がなされています。
古くから社会課題分野においてプログラムの目的や活動を定義する際に使われてきたのが「ロジックモデル」です。ロジックモデルとは、ある施策がその目的を達成するに至るまでの論理的な因果関係を明示したものであり、それを以て「変化の理論」になりうると主張する団体も多くあります。典型的には、「投入→活動→産出→成果」という一連の流れを図で表して表現されます(図3参照)。

ロジックモデルのメリットは、組織内から見えやすい「投入→活動→産出」の枠組みを超えて、その先にある顧客や受益者にとっての成果を明示的に考えられることです。現場は目の前の活動や産出に目を向けがちですが、ロジックモデルによって、活動や産出が、どのような成果あるいはその先にある究極の目標や生み出したい影響につながるのかを理解し、より上位の目的を意識しながら行動することが期待できます。また、反対に経営陣や行政機関などは、最終的な目標にばかり焦点を当てがちですが、ロジックモデルによってどのようなプロセスが目標とする長期的成果に至るかを認識することで、より適切な時間軸で期待を設定すると共に、当面現れる成果や先行指標の重要性を理解するでしょう。
ロジックモデルにはメリットがある一方で、現場の運用においては問題があるとの声がよくきかれます。それは、ものごとを線形に考えているため、現実の社会システムの姿や現場の実態を捉えきれないからです。計画をする組織が自組織の活動を起点に産出、成果を順次考えていくと、成果や究極の目標に資する結果につながることを意識しすぎるあまりに、自組織の活動以外に必要となる諸条件や、自組織が意図せずつくってしまうマイナスの影響を軽視しがちです。
しかし、システム思考が示すとおり、現実の社会システムというものは、フィードバックによる循環構造や蓄積の構造、さまざまな変化における時間的遅れなどがありますが、これらのシステム的な構造がどのように活動や成果に作用しているか、ということはロジックモデルに反映されていません。こうした作用をふまえないロジックモデルは、予期せぬ結果や副作用、リソースの浪費ばかりを生み出し、本書に示しているように意図する問題解決や目標達成がままならない状況を生み出しがちです(図4参照)。

ロジックモデルは経済開発や社会問題の分野で広く普及しているものの、現実的な観点から、モデルのとおりにことが運ぶ可能性が低いという欠点のため、多くの国ではシステム思考のアプローチなどで補完することが要求されています。つまり、まずはシステム思考を用いて「As Is(今の現実の構造)」と「To Be(望ましい構造)」を描き、そのあとに必要なエッセンスを抽出してロジックモデルに落とし込んでいけば、より現実的なモデルとなることが期待されているのです。しかし、現実の重要な要素の多くを除外してしまっている線形のモデルの限界は認識しておく必要があるでしょう。
「変化の理論」は、実のところ、ロジックモデルの問題を克服し、より効果的な方法論を確立するために、リーダーシップ開発や社会的事業の研究を行う〈アスペン・インスティテュート〉における専門家たちの対話によって開発された方法論です。この方法論で作成するのは、ロジックモデルよりも包括的な「アウトカム・パスウェイ」と呼ばれる図です。
アウトカム・パスウェイでは、社会課題に関わる利害関係者たちを集めた参画プロセスを通じて、まず最終的に創出したい数年~数十年先の未来における具体的な社会の変化(ビジョン)を策定し、未来のビジョンを起点として何が変化しなくてはならないかを遡る「バックキャスティング」のアプローチが特徴です。長期的な目標を具体化した長期成果を定め、そして中期、短期にそれぞれどのような成果が生ずる必要があるのか、どのような前提条件が必要となるか、を明示した図を作成します(図5参照)。

アウトカム・パスウェイを作った後に、それぞれの成果を挙げるためにどのような促進要因や阻害要因があるのか、また、関係する諸組織・団体がどの成果を生み出すことをミッションとして掲げ、そのミッション達成のためにどのような投入、活動、産出を行うのかについて、集まった人たちで話し合います。最終的には、諸関係者たちの介入によって、なぜ、どのように変化が起こるかの物語を書きあげます。
線形の思考では該当プログラムによる貢献を過大に見積もり、他の必要条件を過小に見積もる我田引水のような思考になりがちです。しかし、アウトカム・パスウェイのように長期、中期、短期の成果の始点から遡って、自組織のミッションや活動内容を検討することで、望ましい変化が起きるための前提や他組織の成果について必要となる条件を包括的に捉えやすくなります。
変化の理論を作成する際に最も重要なのが、多様な利害関係者たちの参画による学習プロセスです。それによってシステムに関わるさまざまな関係者や要素を表現できるため、より現実的な変化の理論を描きやすくなるでしょう。
個人や組織がそれぞれ単独で考えると、「当然他の利害関係者が前提条件を整えてくれるだろう」「自分たちの焦点を当てるべきはこの範囲だけで十分だろう」と狭い視野になりがちです。しかし、利害関係者たちが集まって互いにどのような前提条件をもっているか、期待しているかなどを明示しながら話し合うことによって、何がボトルネックかについての理解を深めることができます。また、意図せず他者の抵抗を招き入れ、自らの成果にとっても前提条件となる要因に悪影響を与えることを避けられるようにもなるでしょう。このようにして、同じ社会問題に関わる複数の組織やプログラム間において、その関係性や位置づけが明らかになります。
変化の理論は、単に計画や評価のための方法論にとどまることなく、透明性ある包摂(インクルージョン)とエンゲージメントによって、社会の中の組織・個人間の適切なパワー・ダイナミクスを整えるプロセスでもあります。
あなたの組織に求められる変化の理論が仮にロジックモデルの形式をとっていたにしても、ここに紹介したアウトカム・パスウェイの形式であったにしても、本書にあるシステム全体から招集すること、そしてシステム的に考えることによって、より多くの関係者たちの共通理解や調和した行動をもたらし、望ましい成果を実現する可能性を高めることができるでしょう。

●よりよい未来に向けて
システム思考を実践することは、事業、職場、家族、そして個人の諸課題にも応用可能です。日々の出来事レベルのさまざまな問題にただ反応的に対処するのではなく、大局、全体像、根本まで考えて取り組むことによって、よりよい成果と豊かな人生をもたらしてくれます。
同時に、視野が広がることによって、自分自身の行動や身の回りにも存在する、社会や環境の問題に気づきやすくなります。ジェイ・フォレスター、ドネラ・メドウズ、ピーター・センゲ、デイヴィッド・ストローはじめ多くのシステム思考家たちは、社会・環境問題への貢献に人生の多くの時間を投じました。まさに、「義を見て動かざるは勇なきなり」、気づいたことから自分自身や身の回りの変化に取り組むことは可能なのです。
「世界を変える」と言うとき、一人で八〇億もいるすべての人類の行動を変えようとするのはもちろん現実的ではありません。自分の身の回りの現実の世界を考えてみるのはいかがでしょうか。あなたが心血を注いで変えたいと思う「世界」の範囲は、どれくらいの範囲でしょうか? 自分の家族や友人など数人かもしれないし、数十~数百人いるコミュニティや職場かも知れません。あるいは人によってはもっと広い範囲で数多くの人を対象にするかも知れません。
それぞれの世界がよくなり、また、その世界を包み込むさらに大きな世界の中でそれぞれの世界が互恵的な関係を紡いでいければ、その周りに変化が広がっていきます。一〇〇〇人いる組織やコミュニティのシステム構造を改善する変化の担い手が、八〇〇万人集まれば、結果的に世界が大きく変わります。
目の前にいる一人ひとり、そして一つひとつの課題にじっくりと向き合うこと、そしてシステム思考家としてのあり方を探求する道を歩み続けることは、人生をとても意義深いものにしてくれると実感しています。より多くの人の人生を豊かにしながら、社会や環境の問題も解決される世の中となっていくことに、本書が役立つことを願っています。
本書を上梓するにあたり、システム思考や学習する組織の恩師であるデニス・メドウズ氏、故ドネラ・メドウズ氏、ピーター・センゲ氏ら数多くの方たちに感謝の意を表します。また、世界各地で環境・社会問題に取り組む実践者と研究者の国際ネットワーク〈バラトン・グループ〉の仲間たちにはさまざまな問題構造の理解を助けてくれました。また、日本でそれぞれの分野・地域で取り組み、システム思考や学習する組織を導入線とする実践家たちとの議論や行動によって、日本で展開するうえでの実践的な智慧をいただきました。冒頭にまえがきを加えてくれている井上英之さんも、そうした同志の一人です。
捉えづらいシステム思考の文章を何度も練り直すのに、翻訳を一緒に進めた中小路佳代子さん、編集の下田理さんにも大変お世話になりました。そして、この本を手に取り、読んで下さった読者の方に感謝申し上げます。この本が何らかの気づきにつながり、ものごとの見方や考え方について考えるきっかけになればうれしく思います。自分が生まれたときよりも、よりよい社会を後世に残す連鎖が続くことを、心より願っています。
二〇一八年一〇月

[監訳者]小田理一郎
チェンジ・エージェント代表取締役。オレゴン大学経営学修士(MBA)修了。多国籍企業経営を専攻し、米国企業で10年間、製品責任者・経営企画室長として組織横断での業務改革・組織変革に取り組む。2005年チェンジ・エージェント社を設立、人財・組織開発、CSR経営などのコンサルティングに従事し、システム横断で社会課題を解決するプロセスデザインやファシリテーションを展開する。
デニス・メドウズ、ピーター・センゲ、アダム・カヘンら第一人者たちの薫陶を受け、組織学習協会(SoL)ジャパン理事長、グローバルSoL理事などを務め、システム思考、ダイアログ、「学習する組織」などの普及推進を図っている。
ドネラ・メドウズ著『世界はシステムを動く』の日本語版解説を担当。著書に『「学習する組織」入門』共著に『なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか』『もっと使いこなす!「システム思考」教本』(東洋経済新報社)など、共訳書にピーター・M・センゲ著『学習する組織』、ビル・トルバート著『行動探求』(以上、英治出版)、ジョン・D・スターマン著『システム思考』(東洋経済新報社)、監訳書にアダム・カヘン著『社会変革のシナリオ・プランニング』『敵とのコラボレーション』(以上、英治出版)。
『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』の「監訳者による解説」をお読みくださり、ありがとうございます。次回は本書編集者へのインタビューをお届けする予定です。どうぞお楽しみに。
英治出版オンラインでは、連載著者と読者が深く交流し、学び合うイベントを定期開催しています。連載記事やイベントの新着情報は、英治出版オンラインのnote、Facebookで発信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。(編集部より)


