
コレクティブ・インパクト創出、一歩目の挫折から生まれた二歩目:『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』著者来日シンポジウムレポート(竹之下倫志)
一つの組織ではなく、幅広いコラボレーションによって社会全体で問題解決を目指す手法である「コレクティブ・インパクト」。その実践書『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』の読者で、いじめ構造変革プラットフォーム(PIT)共同発起人の竹之下倫志さんに、著者デイヴィッド・ストロー氏来日シンポジウム参加を通して考えたことを綴っていただきました。登壇者たちの言葉もふんだんに引用される本記事、イベントの記録としても役立てば幸いです。
▼竹之下さん執筆の前回記事はこちら
コレクティブ・インパクトの「はじめの一歩」が見つかった感謝の夜
コレクティブ・インパクト実現に向けたステップ
世の中にはたくさんの社会課題が存在する。日本だけでもNPOの数はこの15年で10倍に増え、関与者は50万人を超えた。世界全体では数千万人規模の人間が活動を続けている。
しかし、数多くの課題が今もなお未解決のまま存在している。なぜなら、それらの課題はそれぞれが複雑に絡み合って存在しており、一人、一団体、一国が単体で取り組んでも解決が困難であることが多いからだ。私たちが取り組んでいる「公教育におけるいじめ問題」もそんな課題の一つである。
活動における自分の力不足を痛感する中、その解決策として知ったのが、一つの組織ではなく、幅広いコラボレーションによって社会全体で問題解決を目指す「コレクティブ・インパクト」という手法だった。
以前、その実践方法を紹介した書籍『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』を読み、出版記念セミナーに参加して、コレクティブ・インパクトの実現に向けた一歩目を見据えることができた。それは、本書が最初のアプローチと位置づけている「変革の共通基盤作り」を実現するためのアクションだった。

「共通基盤作り」は、変革プロセスの第一段階だ。このプロセスでは、主要な利害関係者を特定・巻き込んだ上で、「現状の共通認識」と「目指す未来の共有ビジョン」を作ることを目指す。
このプロセスを始める際には、自分の手の届く範囲で立場が違うメンバーを呼び、現状と未来について対話を行うことが大切とされている。私はこの対話こそが自分が行うべき一歩目だと思い、実際に挑戦してみた。そこで起きたことを、まず、ありのままに共有しよう。
踏み外した一歩目…何が間違っていたのか?
私たちは「学校におけるいじめ」の問題解決に取り組んでいる。いじめの被害により、未来や可能性が閉ざされてしまう子どもを一人でも減らすこと。これが、実現しようとしていることである。
いじめを取り巻く環境には数多くの関係者が存在する。被害・加害の当事者、保護者、教員含む学校関係者はもちろん、子どもを助けようとするスクールワーカーやNPO、調査や学校制度の見直しを行う教育委員会や行政、法の側面から事案の解決をサポートする弁護士など。
事案によって関わる人物は違ってくるが、一つ確実に共通することがある。それは、「いじめがあってほしい、子どもが痛んでほしい、と願っている人はいない」ということだ。
だからこそ、私たちが呼びかけると、想いを同じくする人が集まってくれた。いじめ事案に触れた経験を持つ教員の方。教育委員会の立場で子どものケアに関わる方。過去にいじめにあっていた元被害者や、子どもも自分もいじめにあっていたという保護者。そして、政治家として、行政の役割として解決を望む方。
そうして彼らと、前述したような対話の場を実現することができたのだ。微妙な問題でもあるので、お互いの本名は伏せることにした。
しかし、その結果は残念なものだった。
ある教員の方は、「エネルギーがぶつかる場に」という趣旨を理解し、あえて本心を語ってくれた。しかし、その言葉に怒り、傷ついていった保護者もいた。ファシリテーターとして場を進行していた私も混乱してしまい、その状況を見かねた行政の方が代わりにまとめようと動き出す始末だった。ビジョンを共有するどころか、現状の確認にも行きつかないまま、その場は終わってしまった。
もっとも自分に突き刺さったのは、場の終了後に保護者の方から届いたメールでの一言だった。
「つらい場でした。申し訳ないですが、もし次があっても今は参加する気になりません」
0勝1敗。次戦登板予定なし──。これが私の状況だった。システム思考の話ばかりして、最近仲間から呼ばれるようになった「システムシンカー(システム思考家)」というあだ名が、皮肉にしか聞こえなくなってしまった。
果たして、自分のアプローチには何が不足していたのだろうか。
それが見出せないままでは、いじめ問題解決に向けたシステムを育てるどころか、何度も同じ事態を起こしてしまうだろう。ましてや、今のメンバーは想いに共感して集まってくれてはいるが、そこに強制力はない。何度も失敗できるわけではないのだ。
何が足りないのか?
アプローチ自体が間違っているのか?
前掲した書籍『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』の著者であるデイヴィッド・ストロー氏の来日イベントが開催されたのは、そんな悩みを抱え、次の一歩を見失っていたときだった。
デイヴィッド・ピーター・ストロー(David Peter Stroh)
システム思考をベースに組織や社会課題の解決を支援するコーチ/コンサルタント。ブリッジウェイ・パートナーズ、アプライド・システム・シンキングの共同設立者。ピーター・センゲの「学習する組織」の方法論を用いた組織学習専門のコンサルティングファームであるイノベーション・アソシエイツの設立にも携わる。
社会変革プロジェクトに25年以上携わり、世界銀行、ロイヤル・ダッチ・シェル、W・K・ケロッグ財団など、様々な非営利組織、営利組織、公的機関と協働した実績を持つ。
「実現したい未来像」を語るよりも先に大事なこと
「実現したい未来像」を語るよりも先に、やるべきことがある──。
そんな話からデイヴィッド氏のレクチャーは始まった。最初にやること、それは、「今の現実」を理解することだという。
「創造的緊張(クリエイティブ・テンション)」という概念がある。これは、「今の現実」と「実現したい未来」を点としたときに、その間に張られたゴムのようなものでよく例えられる。

一つ例を挙げよう。最近よく耳にする「ブラック校則」。髪の黒染め強制や下着の色指定・チェックのようなものだ。ともすれば人権侵害とも言われかねない校則が問題になったときに、様々な対処法が存在するだろう。
例えば、「その校則を学校側が廃止する」という手段がある。他の案としては、「そもそも校則を決定・見直しするプロセスに生徒や保護者を巻き込み、関係者間で合意をとれる校則が生まれる仕組みを作る」といった、今後の学校の在り方を問い直すところから始める方法もあるだろう。
この場合、恐らくは前者のように校則を廃止するだけのほうが実現しやすいだろう。なぜなら、「今の現実」と「実現したい未来」の間にある距離は、後者の案より近いからだ。二つの点が近ければ、その間にあるゴムの緊張は強くない。元の点(現実)に戻ろうとする力(=抵抗勢力)は弱い。
では、学校の在り方から問い直していく場合はどうだろうか。二つの点は遠く、緊張は強い。元の点に戻ろうとする抵抗力は強いだろう。一方で、実現したい未来がよりチャレンジングで、皆が魅力的だと感じられる可能性が高いため、先の点(未来)に進もうとする力も強く働いていく。結果、より本質的に、社会や未来を大きく変えることができるかもしれない。
だからこそ、「リーダーは実現したい未来を具体的に、魅力的に語る必要がある」と私も考えてきた。起業家が資金調達の際に実施するピッチ(プレゼン)で目指す世界観を語るのは、その典型だろう。
しかしデイヴィッド氏は、まず関係者の間ではっきりと認識を揃えておくべきなのは、「実現したい未来」よりもむしろ「今の現実」のほうである、と語る。
(以下、敬称略)
デイヴィッド:リーダーなら、ビジョンを作らなくてはいけない。そう考えている人も多いと思う。確かに、ビジョンを示せば皆が未来を見ることができるようになる。でも、それだけだと現実は見えていない。現実の構造がどうなっているかを見ることができていない。本当に難しいのは、共有された現実像を作るほうだ。
緊張構造は、二つの点の間で発生する。行きたい未来の点だけ固定しても、現実の点が固定できていなかったら、そこに緊張構造と大きなエネルギーは発生しない。言い換えれば、行くべき先が分かっていても、今の現実が分かっていなければ、そこにたどり着くことはできない。

確かにこれは、実現したい未来への想いが強いほど、見落としてしまう観点かもしれない。「ブラック校則」の事例でも、「なぜこれまでそれが受け入れられてきたのか?」「そこにはどういう背景があるのか?」「それぞれの関係者たちは、校則という存在にどういう思いを持っているのか?」…...様々な問いを経て、先に現在の構造を皆で認識しなければ、有効な変え方も見えづらいだろう。
デイヴィッド:「現実」には複数のレベルが存在する。「起きる様々な出来事」「それらの傾向」「それらが発生する構造」…...。今何が起きているのか? これまで何が起きてきたのか? それはなぜなのか? 現状を変えようと努力しているのに、なぜこれらが起きてしまうのか? このような、構造への理解を深めるためのアプローチはインパクトを生み出せる。
答えられない問い──「今の問題に対して、あなたはどう加担していますか?」
しかし、ここでやはり冒頭の悩みに戻ってしまう。「今の現実」を理解する上でも、関係者間の対話が不可欠。しかし、今の問題は「その対話がうまくいかない」ということなのだ。
そんな疑問を見透かすように、デイヴィッド氏は対話におけるキーポイントについて語り出した。それはいくつかの「問い」に関するものだった。
デイヴィッド:大切なのは、皆の「課題に対する認識」を揃えること。そのためには、議論の焦点を絞り、皆がどう「問題に貢献しているか」を明らかにする必要がある。
そのために有効な問いが二つある。まず焦点を絞るために、「なぜ自分たちは最善を尽くしているのに、この問題を解決できずにいるのか?」と問うこと。そして次に、「あなたが、無意識にせよこの問題に加担してしまっているのはどの部分ですか?」と問うことだ。
焦点を絞る問い。これは確かに自分に不足していたと思わされるものだった。お互いの本音を話す、そんなスタンスで対話を進めていたが、「本音」という切り口では発言した「個人の感情」が目立ち、感情の応酬になってしまう。
私たちがフォーカスすべきであったのは個人ではなく、その人が置かれていた「立場」であり、その立場の人がそう行動してしまうように規定する「関係構造」だった。そこに目を向けるためには、「最善を尽くしているのに、なぜ問題を解決できずにいるのか?」と問うアプローチが必要だったのだろう。細やかな問いの難しさを、あらためて痛感した。
しかし、次の問いは理解を超えるものだった。
無意識にせよ、あなたがこの問題に加担してしまっているのはどの部分ですか?
これは、「自分が課題を生み出してしまっている」ということなのか?
自分が今のいじめ問題の事態を悪化させていることは何か──。
この問いは、私自身にとって思いもよらないものだった。傲慢かもしれないが、今の仕組みや取り組みでは救えない子がいるからこそ、私たちが手を伸ばさなくてはならない…...そんな風にすら思っていた。
そんな驕りを打ち倒すようにデイヴィッド氏は続ける。
デイヴィッド:私たちは「他の皆が変わったらうまくいくのだ」「自分は問題の外にいるのだ」と思ってしまいがちだ。
今あるシステムは、今起きている問題を引き起こすように完璧にデザインされている。そのシステムの中にいたままで、人やお金といったリソースを使って自分の活動を広げようとするとどうなるか...…今のシステムと、そこから生まれる現在の問題を強化してしまうだけだ。自分が問題の一部であることを忘れてはいけない。
そして、次の言葉が私にとどめを刺した。
デイヴィッド:自分が問題の一部であることを理解していなければ、解決策は見つからない。
「他の人たちを変えよう」という姿勢では変わらない。システムを変える上で一番大きな力を発揮するのは、あなたが「自分自身の考え方や意図、行動を変化させていくこと」だ。
誰もが世界を変えたがっている。でも、そのためにはまず自分を変えなければ、とすぐに思える人は一人もいない。

「自分が原因の一つである」と認めることの難しさ
果たして、自分の活動が本当に現在の問題を強化してしまっているのだろうか?
だとしたら、どのように強化してしまっているのだろうか?
私は何を変えればいいのか?
その場で考えても、すぐに答えは出なかった。苦しみ助けを求めている子どもたちが確かに目の前に存在しているから、その子たちに手を差し伸べる。それは今すぐにでも必要なことなのではないのか。何の問題を生むのだろうか。
──これが、「未来は見えていても、現実を見られていない」ということなのか?
会場でも、私と同じ気持ちに至る人が多かったようだ。「自分が問題に加担している、と認めるのは難しい」、途中の参加者同士の対話の時間で、そんな声も聴こえてきた。
モヤモヤと頭の中を消化しきれない中、セッションはシステム的なアプローチで児童労働の問題に取り組む認定NPO法人ACE(以下ACE)岩附氏の活動の話を経て、全体での感想のシェア、そして井上氏、小田氏を交えたデイヴィッド氏とのクロストークに移っていった。
岩附由香(いわつき・ゆか)
認定NPO法人ACE代表、2019 G20市民社会プラットフォーム共同代表、2019年C20議長。14~16歳まで米国ボストンで過ごし、桐朋女子高等学校卒業。上智大学在学中、米国留学から帰国途中に寄ったメキシコで物乞いする子どもに出会い、児童労働と教育を研究テーマに大阪大学大学院へ進学、国際公共政策修士号取得。在学中にカイラシュ・サティヤルティ氏(2014年ノーベル平和賞受賞)の呼びかけた「児童労働に反対するグローバルマーチ」をきっかけにACEを発足させる。その後、NGO、企業、国際機関への勤務やフリー通訳を経て、2007年よりACEの活動に専念。2017年アルゼンチンでの第4回児童労働世界会議では発表を行うなど、国内外のアドボカシー活動に力を入れている。夫と2人の娘の4人暮らし。
井上英之(いのうえ・ひでゆき)
慶應義塾大学 特別招聘准教授、INNO-Lab International 共同代表。ジョージワシントン大学大学院卒(パブリックマネジメント専攻)。ワシントンDC市政府、アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア)を経て、NPO法人ETIC.に参画。2001年より日本初のソーシャルベンチャー・プランコンテスト「STYLE」を開催するなど、国内外の社会起業家育成・輩出に取り組む。2003年、社会起業向け投資団体ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京を設立。2005年より、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスにて「社会起業論」などの、実務と理論を合わせた授業群を開発。「マイプロジェクト」と呼ばれるプロジェクト型の学びの手法は、全国の高校から社会人まで広がっている。2009年に世界経済フォーラム「Young Global Leader」に選出。近年は、マインドフルネスとソーシャルイノベーションを組み合わせたリーダーシップ開発に取り組む。
訳書に『世界を変える人たち』(ダイヤモンド社)、監修書にデービッド・ボーンステイン、スーザン・デイヴィス著『社会起業家になりたいと思ったら読む本』、加藤徹生著『辺境から世界を変える』(ダイヤモンド社)。
小田理一郎(おだ・りいちろう)
チェンジ・エージェント代表取締役。オレゴン大学経営学修士(MBA)修了。多国籍企業経営を専攻し、米国企業で10年間、製品責任者・経営企画室長として組織横断での業務改革・組織変革に取り組む。2005年チェンジ・エージェント社を設立、人財・組織開発、CSR経営などのコンサルティングに従事し、システム横断で社会課題を解決するプロセスデザインやファシリテーションを展開する。デニス・メドウズ、ピーター・センゲ、アダム・カヘンら第一人者たちの薫陶を受け、組織学習協会(SoL)ジャパン理事長、グローバルSoL理事などを務め、システム思考、ダイアログ、「学習する組織」などの普及推進を図っている。ドネラ・メドウズ著『世界はシステムを動く』(英治出版)の日本語版解説を担当。共著に『なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか』『もっと使いこなす!「システム思考」教本』(東洋経済新報社)など、共訳書にピーター・M・センゲ著『学習する組織』、ビル・トルバート著『行動探求』(以上、英治出版)、ジョン・D・スターマン著『システム思考』(東洋経済新報社)、監訳書にアダム・カヘン著『社会変革のシナリオ・プランニング』『敵とのコラボレーション』(以上、英治出版)。
私のモヤモヤを代弁してくれるように、岩附氏は他の3名に問いをぶつけてくれた。
岩附:「自分が原因の一部である」という感覚を、まだそこまで持てていないなと感じています。「自分がシステムの一部である」ということは理解しているのですが。良いことに対しては認識があるんです。「あ、これをやったから、こういう風に良い形で私たちに返ってきた」みたいに。だけど、悪いことについては見えていない。どうしたらそこに気づけるのかな?と思います。
その問いの答えとして展開されたのは、「Self-Awareness(セルフ・アウェアネス)」と呼ばれる領域の話だった。
セルフ・アウェアネス──
一般的には、「自分自身に気づき、理解すること」を指す。
昨今書店で多く並んでいる「Mindfulness(マインドフルネス)」に関する本の中でもよく目にする言葉だ。話を聞いていくと、このセルフ・アウェアネスは、自身が問題に加担していることを自覚するのに役立つだけでなく、社会課題と向き合う姿勢全般の土台となるものだった。
社会や組織という大きな存在に対する変革の中で、なぜ「自分」という個に向かうことが重要なのか?

社会課題と向き合う上で「セルフ・アウェアネス」が重要な3つの理由
デイヴィッド氏、小田氏、井上氏より、様々な切り口で語られる「セルフ・アウェアネス」。社会課題に立ち向かう上でのその重要性は、大きく分けて3つの点で述べられていた。
まず一点目は、「自身と繋がることが、社会やシステムと繋がる第一歩になる」ということだ。
まずは、物事に対する自分の感情、考え、行動をメタ認知し、そこで気づいた事実を理解し、自覚し、受け止めること。それにより、ともすればどこか遠かった社会課題と自分との繋がりを認識することができる。
例で挙がったのは、海洋プラスチック問題とペットボトルだ。
海洋プラスチックごみ問題が話題となって久しい。ウミガメに突き刺さるプラスチックストローの動画を観て、ショックを受けた人も多いだろう。しかし、その動画を観て「この問題を解決したい」と感じたはずの自分も、ふとした瞬間に、自動販売機でペットボトルを購入している。
想いと行動に矛盾がある。しかし、自分を責める意味合いで認識しろ、というわけではない。
「課題は分かっている。でもふとしたときに、その想いに反する行動を取ってしまう」、そんな自分は、普段どんな環境にいて、どんな情報に接していて、どんな想いで行動しているのか。その行動は、どんな構造によって発生するものなのか。
そんな背景構造に気づけると、「自分と同じような人もいるのでは」と思える瞬間がくる。そして、自分とシステムが繋がっていて、自分はシステムの中にいるということに気づく。
井上:システム思考(Systems thinking) よりも、まずはシステムへの気づき(Systems awareness)が大切です。毎日の習慣など、日常の身近な小さなことでいいです。意図と結果が違い、望んでもいないのに繰り返されてしまっている状況を話してみてください。
いつも自分はどんな気持ちで、何を考えて(もしくは無意識に)、どういう行動をしていたのかに気づく。それに気づいたとき、それと同じ構図が他の人にもあって、そしてそれが世の中にも存在していて、自分はそのシステムの縮図なのだと気づけます。
一番大事なのは、感情をはじめとした自分自身の「今の状態」に気づいていること。例えば、自分が寂しいと感じていたとしたら、そんな「寂しい自分」に気づく。その自分を否定していると、寂しい自分にイライラするので、寂しい他者に出会うとやはりイライラしてしまい、受け入れられない。「いや、お前だけじゃないよ」って。でも、自分自身が「こんな背景で寂しいこともあるよね」って自分に共感ができていたら、寂しい他者に会ったときも、「あ、そうだよね」って理解できるようになります。そこから世界と繋がります。

二点目は、「セルフ・アウェアネスは今の現実とだけではなく未来のビジョンとも密接に関係しており、ビジョンの明確化は社会課題と向き合う上で生じる痛みや抵抗感を乗り越える力になる」ということだ。
まず、前述した「自分が問題に加担していると認めること」のような痛みや抵抗感を乗り越えるために、なぜビジョンの明確化が役立つのか?
井上:社会課題に向き合う上で生じる痛みや抵抗感を受け入れるには、欲しい未来を明確にすることが役に立ちます。自分の気持ちや行動がどんなメカニズムで起きているのかに気づきつつ、その行動の先にある欲しいゴールが明確に見えたとき、新しい行動の選択肢が出現します。
自分がどんな社会を望んでいるのか。そんなビジョンがはっきりし、そこへの情熱をしっかりと抱けるようになれば、出現したより望ましい行動への情熱によって「自分が事態を悪化させている」という信じがたい事実にもあらためて向き合うことができる。これは直感的に理解できる部分だった。
しかし、ビジョンの明確化の効能は、それだけではないという。ビジョンを明確化するそのプロセスにこそ、自分の行動や意識を変える機会が存在していた。このプロセスはまず、自分のビジョンが明確でない、という「気づき」から始まる。
いじめのない世界、いじめによる自殺者ゼロの世界って、どんな世界なんですか?
参加者同士の対話の時間の中で発せられたこの質問に、私はすっと答えることができなかった。これは、明確だと思っていた自分のビジョンが、実は明確ではなかったと気づいた瞬間だった。
この問いをきっかけに、「本当は自分は何を望んでいるんだろう」「それはなんでなんだろう」、そんな思考が自分の中で始まった。
気づきが起きると、その理由を求めて、自分や周囲との対話や内省のプロセスが始まる。この過程で生み出されるセルフ・アウェアネスこそが、抵抗感を乗り越え、自分の行動を変えるカギになるという。
この記事の執筆過程における対話の中で、井上氏は次のように述べていた。
井上:ビジョンについて対話することで、自分自身を多様な角度で観察することができます。その良さも可能性も、持っているものや恐れも、欲している未来も。また自分を理解するようにチームのメンバーや、課題に関わる多様な他者を理解することができます。
ビジョンが不明確であったことへの気づきをきっかけに、内省の中で自分の深い部分に潜っていく。そこで認識する、普段は言葉にしない自分の複雑な感情や欲望。そうした内面に気づき、「同じようなことが他の人の中にもある」と腹落ちしたときに、自分自身も、課題を取り巻く周りの人をも受け入れて理解できる瞬間がくる。これが、自分の行動を変えるきっかけになるのだ。
しかし、自分の内面に深く向き合うことは簡単ではない。そこにあるのは前向きな想いだけではないからだ。思わず目を背けたくなる、言葉にできないドロドロした複雑な感情も含まれるのだろう。
私自身もそうだ。自分と向き合う中で、過去のいじめを受けたシーンもあらためて頭に浮かんできた。
自分や周囲がいじめの中で受けた体験と、そこから変わってしまった人の見え方。そうしてネガティブに見えてしまう人たちに対する不信や、怒り。だからこそ、自分こそが助けるべきだ、というある種傲慢な想い。自分の子どもにはそんな経験をさせたくないだけ、という個人のエゴに過ぎない衝動。
そんな内面が存在することを認めるには、痛み、苦しみを伴う。しかし、この痛みは当然発生するものであるし、同じ課題を取り巻く人たちの中にもあるものだ。だからこそ、自分の痛みを通じて、彼らのリアルな感覚を確認できるようになるのではないか。そうして課題を生んでいる姿が一つ理解でき、自分たちが向かう方向が一つ見えてくる。
つまり、自身の痛みの認識(セルフ・アウェアネス)を通じて、向かうべきビジョンがより明確になっていくのだ。
ビジョンと痛みは相関の関係にあり、痛みを感じることは必要かつ当然のプロセスなのだ。そう捉え直したとき、痛みと同時に、やわらぎが発生するような、不思議な感覚を覚えることができた。
ACEも同様に、痛みを伴う気づきからあらためて自分たちと向き合い直した。その後に起きた変化は、まさにセルフ・アウェアネスがビジョンを明確化した好例だと感じる。
岩附:ACEの元々のミッションステートメントは「児童労働の撤廃と予防を市民とともに行います」というものでした。でも、私たちが欲しい世界が「児童労働がない世界」だとしたら、「児童労働がない世界ってどういう世界なのか」という問いに、このミッションは答えていないことに気づきました。だから、ACEはミッションを変えました。具体的にはミッションではなくPurpose(パーパス:究極的な存在意義)として、「私たちは、子ども、若者が自らの意志で人生や社会を築くことができる世界をつくるために、子ども、若者の権利を奪う社会課題を解決します」と定義したのです。つまり、この新しい文言の中には、「児童労働」という言葉は入ってきませんでした。

第三者として社会課題に挑むときに陥りがちな罠
セルフ・アウェアネスが重要である理由の三点目として挙げられたのが、「第三者として問題を俯瞰して客観的に関われている、という誤解を回避できること」だ。
今発生している社会課題に社会起業家として挑むとき、ともすれば人は、第三者として、システムの外からその課題を解決しようとする立場に自分を置いて物事を考える。それは私自身を振り返ってもそうだった。その傲慢さに罠が潜むという。
小田:単に「システム思考で合理的に問題を解決しよう」とだけ考えてしまうと、場当たり的で問題を加速させる可能性のある行動はやるべきではない、というのが正論になります。例えば、目先の困っている人の緊急支援だけに注力することなどです。
ですが実際には、現場の中に入ると思わず助けざるを得ない状況が存在するのも事実です。そんな中で、第三者の立場でループ図を描いて「今の対応だと問題を加速するかもしれない。システム思考的には●●の対応をしたほうがいいですよ」と迫っても、実は深くシステムに入り込めているとは言えない場合があります。
第三者という立場を取ると、「全体像をちょっと遠くから見ているつもりになっているだけ」になりがちです。システムに関わる一人ひとりをきちんと生身の人間と認識し、共感を持って「この人の目からは、問題はどのように見えているのだろう」という意識でシステムを捉えようとしなければなりません。
自分に矛先を向けるには、「自分がどんな前提に立っているのか」をいつも意識すること。そして、「その前提が私たち全員にとって役に立つのか」という疑問を常に持って問い続けることが必要です。そのためにはまず、自分がどんな前提やメンタルモデルを持っているのかを理解する必要があります。
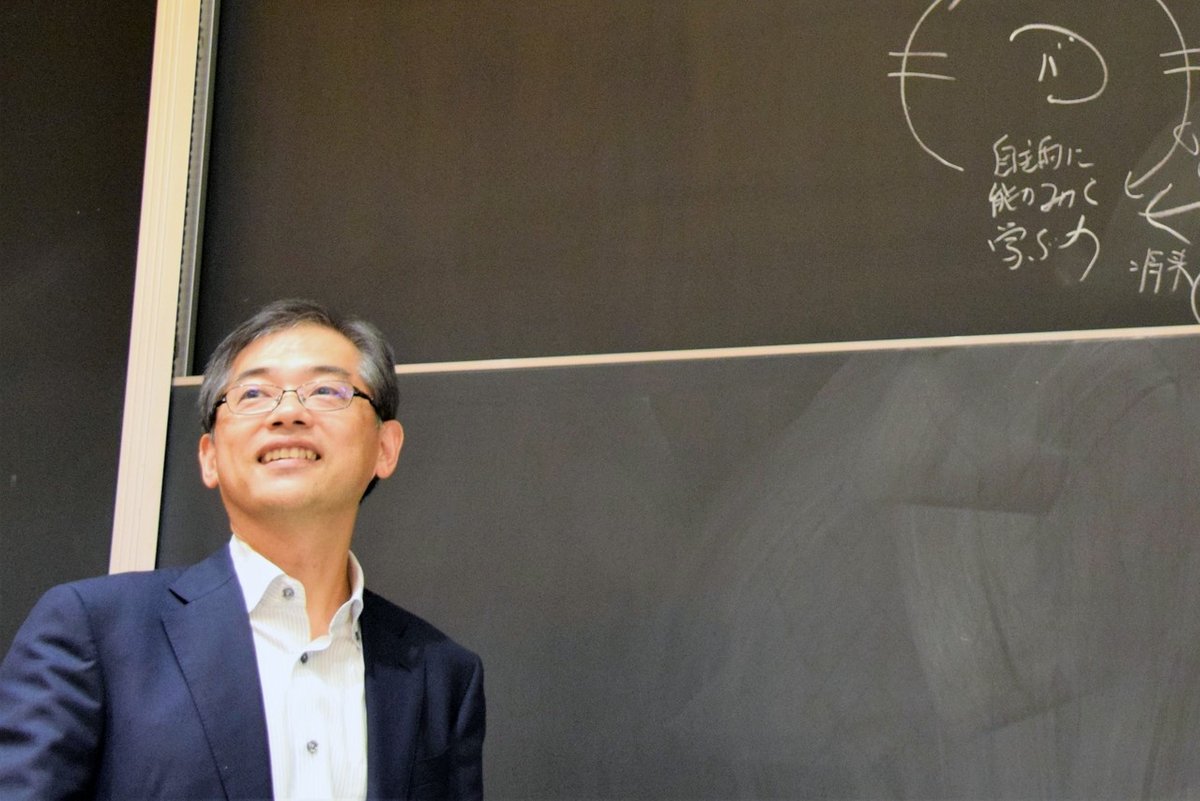
第三者として問題を外から客観的に眺めることで、構造のゆがみに気づき、解決策を講じることができる……私たちはそう考えがちだ。
しかし、システム全体を客観的に理解することは、実際には不可能である。把握したつもりになっても、「少し離れた視点から見ているだけ」に過ぎない。なんらかの立場(例えば「何かの課題を解決したい」「誰かを救いたい」)から行動を始めた時点で、実際は第三者ではなくなっているのではないだろうか。
本当の意味での第三者、つまり問題に対して関わりのない人間であるのは困難であり、それに気づくことは難しい。実際に行動を起こすような、想いが強い人間であれば、なおさらだ。しかし、人はその事実を忘れてしまう。もしくは認識できない。しかし、それに気づかなければ、システムを深く変えることはできない。
第三者であろうとすること。まずはそれ自体を諦める必要があるのかもしれない。私たちも、システムの中では確実に一人の当事者なのだ。
デイヴィッド:「物事が実際にうまくいく」ということと「物事はこんな風にうまくいくべきだ」という私たちの感覚の間にあるギャップに気づくことが大事だ。
自分に足りなかったもの、そして歩み始めた二歩目
ここまで来て、最初の取り組みにおいて、私に足りなかったものが見えてきた。
一言で言うと、私は自分自身にも、システムにも、本当は気づけていなかった、ということだ。そんな状況では、他人同士の対話の中で本音を受け止め合い、理解させることなど、できるはずがなかった。
そうなった理由の一つは、先に出てきたような思い上がりから来るものだったかもしれない。
自分は、当事者ではなく、離れて物事を見えるから、第三者的に構造を理解できている。今の問題に気づけている。だから有効なアプローチをしているのだ…...
そんな傲慢さがあるために、自分自身も課題の一部であると自覚し、それと真剣に向き合うことを怠っていた。
そしてもう一つの理由は、心の底にある恐れかもしれない。自分が課題の発生のサイクルに悪い意味で貢献してしまっていると認めると、自分のこれまでの取り組みが崩れ、共に向き合ってきた人たちを追い詰めてしまうことになるのではないか。それは、自己否定そのものでもある。そして、なおのこと「その事態を解決しなくてはならない」という責任のようなものを負うことになる。その怖さによって、あえて目を背けていたのかもしれない。
しかし実際には、そんな自分に気づいたとき、「周りの人たちもそうなのかもしれない」と感じることができた。ふっと肩の荷が少し楽になった気もした。

イベント以降、あらためて、自分自身や団体のメンバーと、対話の中で自分自身のメンタルモデルに向き合うところから活動を再開した。それを実行したことで起きた変化を、記事の締めくくりとして紹介したい。
まずは、「人と立場」の見え方が大きく変わった。
一緒に最初の共通の基盤を作る際に誰を巻き込むのかを考えるとき、当初は多様な立場・視点を「社会的属性」「肩書」のようなもので確保しようと選択してしまっていた。例えば、政治家、教育委員会、教員、という形だ。
しかし今は、社会的属性ではなく、それ以前にある「個人としての想いと立場」という部分に着目するようになった。「この人は、現在どういう方向を向いていて、どういう視点を持っているのか」「どんな願いによってその役割を担っているのか」、そこを軸にして必要な人を選ぶようになった。
社会的属性は、あくまでそこに影響を与えているに過ぎない、従属的なものだった。それに気づいたとき、よりクリアに必要な人たちの顔を思い浮かべることができるようになった。
次に、「責任」というものに関する捉え方が変わった。
「自分が課題を悪化させている」と認めたとき、これまでの行為に対する責任を重く背負った気持ちに一度はなった。「分かったつもりになって何をしていたんだろう」「これまで悪化させてきた責任をとらなくては......より覚悟を決めて挑まねば...…」そんな想いも確かに持った。
しかし、二つのことが、「責任」ということの重みから自分を楽にさせてくれた。
一つは、責任を「過去に対する自責」ではなく、「未来に向けて選択する責務」と捉え直せたことだ。会が終わった後の登壇者の方々との会話、またこの文章を書く中でのやりとりが、私にそれを気づかせてくれた。
小田:「責任」を考える前にまず大事なのは、「問題への自分の貢献/加担」を認識することです。そうして「今の現実」を認識することで、目指したい未来との間に創造的緊張が生まれます。その後の段階になってから、「では、自分が果たすべき責任とはなんなのか」を再定義していくのです。
まずは、自分が今問題に貢献・加担している事実に気づくこと。そのステップの後、創造したい未来を選んだ段階ではじめて、「自分が果たすべき責任」を定義することができる。責任とは、過去を背負うことではなく、未来によって、選択できるものなのだ。自分の現状を責めるためのものではないのだ。
この気づきは、私の「責任」に対する受け止め方を大きく変えてくれた。
二点目は、責任を「力」として捉えられるようになったことだ。今私がやるべきことだと考えているのは、自分が陥った思考に同じように行きつき、同じように悩むであろう、システム内の人たちに対して向き合うこと。そして、彼らと一緒に課題や可能性に気づき、お互いを認め合い、新たに歩んでいくことだ。そこには、「前向きな後悔の念」とも言える不思議な気持ちがあった。
そんな気持ちを人に話していると、こんな言葉をかけていただいた。
それはresponsibility(責任)と捉えていたものが、response-ability(反応する能力)に変わったのかもしれませんね。
一時は重く感じてしまっていた責任。でもそれは責任ではなく、その課題に対して反応することのできる新しい「力」、だったのかもしれない。
デイヴィッド:私は、「その課題について、あなたにはどんな責任がありますか?」と聞くようにしている。すると、侮辱されたと捉える人もいる。怒って帰っていく人たちもいる。それでも、受け入れてくれる人たちとだけでもその問いを深めていくと、彼らは自分が問題にどう加担していたのかを発見する。同時に、その人たちはそのことをすごく嬉しくも思う。なぜなら、「自分は何をしたほうがいいのか」ということに気づけるからだ。

今、二歩目として私が取り組んでいることは、自分がこれらのことに気づくまでに必要だったステップを、同じ課題に取り組む仲間たちに広げていくことだ(ひょっとしたらこのエッセイ自体も、そんな位置づけなのかもしれない)。
ただ、啓蒙的に広げようとした瞬間、また自分自身の第三者感、驕りが顔を出す感覚もある。
そうならないよう、プロジェクトのメンバー内はもちろん、私たちの活動やこの課題に直接は関係していない外部の方とも、定期的に対話の機会をいただくことで、自分たちの状態を再確認しながら進めている。また並行して、自分たちが目指している世界観もより解像度を上げたものとなるよう、内外との対話やその他のインプットを元にブラッシュアップを続けている。
対話による皆との相互理解・世界観の共有の重要性をあらためて感じ、いじめ領域での実現を一つの大きな目的とする団体「いじめ構造変革プラットフォーム(PIT)」をこれまでの活動とは別に立ち上げ、こちらも手探りながら進めている。
この方法では、正直なかなか課題の解決に大きくは進まない。アクセルを踏んで、もっと早く苦しむ人を救いたい、そんな気持ちになることもある。
しかし、深く課題解決に向かっていくステップとして、これらは必ず必要なものなのだろう。同様にコレクティブ・インパクトに挑んだ先駆者からも、「共通の基盤を築くには、最低8か月はかかる」という言葉をいただいた。しかし、変化が発生したときには、その効果は指数関数的に表れた、という。
指標を与えてくれる先人が存在すること、そして、悩みながら歩むことを許容してくれる仲間に囲まれていることのありがたさを感じながら、迷いながらも二歩目を踏み進めていこうと思う。

※執筆者の前回記事はこちら↓
執筆者プロフィール

竹之下倫志(たけのした・さとし)
一般社団法人HALOMY理事、いじめ構造変革プラットフォーム(PIT)共同発起人。
グロービス経営大学院(MBA)修了。総合電機メーカー、会計系ファームを経て現職。
自身のいじめや不登校に関する経験から、いじめ問題の解消、子どもが安心安全の中で学べる環境の構築に強い関心を持つ。
同じ想いを持つ仲間と2020年にPITを設立、子どもたちを取り巻く環境構造の変革に取り組んでいる。
第一期『シン・ニホン』公式アンバサダー、2018年度英治出版編集パートナー。
新着記事のお知らせや関連情報は、英治出版オンラインのnote、Facebookで発信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。(編集部より)

