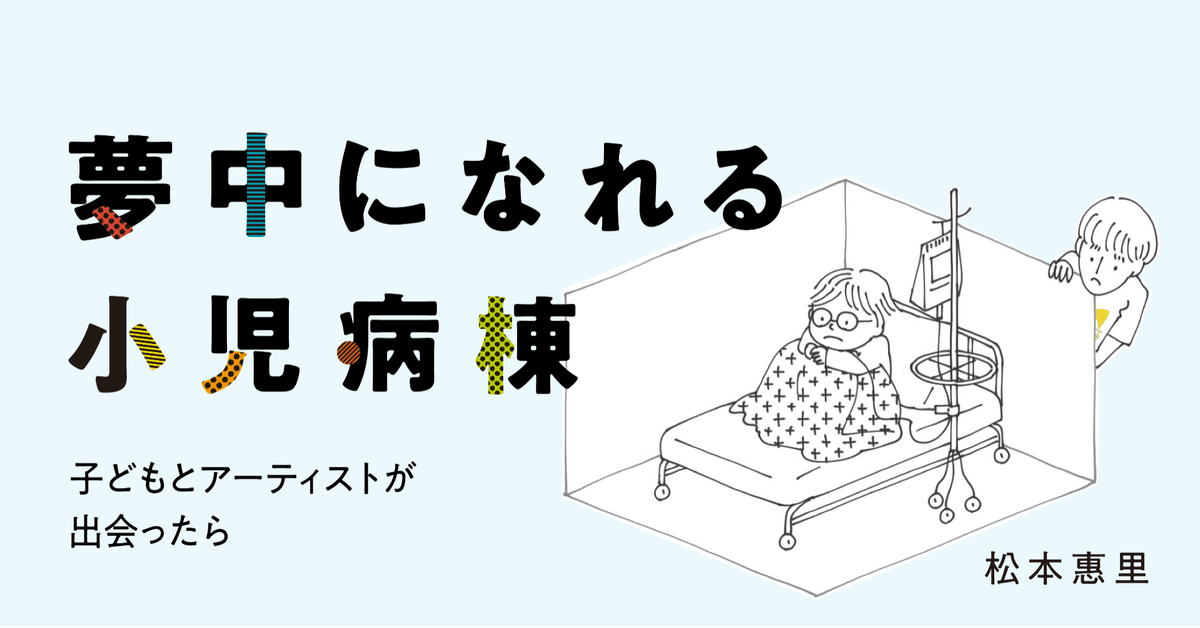
患者になったその日から、私は「できない」だらけになった(『夢中になれる小児病棟』の第1章冒頭部分を公開します)
6月9日発売の『夢中になれる小児病棟――子どもとアーティストが出会ったら』(松本惠里著)。長期入院する子どもたちにアートを届ける活動の経緯と思いを綴った一冊です。
活動をはじめた背景には、著者自身が長期入院した経験がありました。突然の交通事故。気がついたときには病院のベッドの上、長期入院の生活が始まります。治療の緊張感と、わきあがってくる未来への不安──。みなさんは、入院生活が日常になったらと想像したことはあるでしょうか? 本書の「第1章 患者になってわかったこと」冒頭部分を公開します。
私が患者になった日
2000年6月20日。この日の記憶は午前6時20分まで。私は交通事故に遭遇しました。早朝の交通ニュースは、この事故とそれに伴う停電や渋滞を伝えていたといいます。
大型トラックとの出合い頭の衝突事故の瞬間から意識不明となり、その直前のことすら記憶にありません。脳挫傷と肋骨の多発骨折による血気胸で、病院に運びこまれた当初は、いくつもの管が身体につけられていたのだといいます。幸い脳挫傷による出血は早い段階で止まり、肺からの出血が止まるかどうかが生死を分けるハードルでした。
「奇跡が起こった。肺からの出血が治まってきたよ! 助かったんだ!」
朦朧とした意識のなかで、命を取り留めたことを、覗き込みながら息を弾ませ伝えてくれた担当救命医の満面の笑顔は、今もはっきりと脳裏に焼きついています。
このあと、少しずつ肺の状態が回復し、右肩甲骨複雑骨折の手術を受ける態勢が整ったのは入院してから3週間後。救命救急センター、ICUを経て、半日かけて手術をしたあとは一般病棟へ移動することになりました。
このころには意識ははっきりとしていましたが、上半身はコルセットで固められ、右肩から手首まではギプスと包帯でぐるぐる巻き。当然ベッドから離れられません。ギプスから覗いた右手は、指先まで自分の意思ではまったく動きませんでした。動かそうという気力さえなかったように思います。点滴に耐えられる血管を求めてやがて足の甲に針が常に刺されるようになり、かろうじて握力のあった左手に、ナースコールが握らされていました。
自分には縁のないことと思っていた、長期入院生活。患者として長期間ベッド上で過ごすということ。治療を受けるだけの存在になった私は、無力感、やるせなさで心を塞いでいました。身体が動かないぶん、頭のなかではあれこれとマイナスのことばかりがぐるぐると忙しく浮かんできます。
事故の前にしていた教員免許取得に向けた勉強も、子どもたちと週に2回通っていた剣道も今はできない。何気なくしていた愛犬の世話や庭を手入れする瞬間が、とても尊いことのように思えました。
これからはどうなるのだろうか。
いつまでこの生活は続く?
退院したとして、この腕は動くようになるのだろうか。
動かないとしたら、好きな運動はできなくなる?
子どもとの夏休みの旅行は……。
英語教員の夢は諦めるしかないだろうか。
ベッドに横たわって天井を眺めていると、過去の自分への羨ましさと、未来への不安が、頭のなかを絶え間なく駆け巡ります。今になって思い返すと、あのころの私には、「今」の自分に目を向ける時間がありませんでした。苦痛や不安、無念さが怒涛のように押し寄せてくるなかで、今の自分がやりたいこと、今の自分が楽しむことに目を向ける余裕なんてなかったのだと思います。ひたすら治療を受け、手当てされる無力な抜け殻の日々。自分というものがなくなるような感覚でした。
天井を眺めながら、じっと周りの音を聞いていました。動き回る白衣が擦れる音、響く電子音、そして行ったり来たりする看護師さんのパタパタという足音。しまいにはこの軽やかな足音は○○さん、この重々しい足音は○○先生と、足音の持ち主まで判別できるほどになっていました。
あ、誰かが点滴台を押しながら廊下を歩いてくる。さっき出ていったこの部屋の窓側の患者さんが戻ってくるのかな。医療器具が載せられたステンレス製のトレーが、ワゴンに揺られてカタカタとやってくる。どこかの部屋で誰かがナースを呼んでいる。ナースの小走りが続く。あの音は夕飯を運ぶワゴンに違いない。心なしか病院食の匂いが一緒に運ばれてくる。
そんなふうに一日が過ぎていきます。音があってよかった。匂いがあってよかった。音と匂いで情景を想像して楽しんでいました。空想は身体が言うことを聞かないなかでの、ささやかなエンターテイメントでした。
長く長く、ひたすら長く感じられる一日。単調で退屈な一日のなかで、唯一の自由であるそんなささやかな空想にも、痛みと不安が邪魔をします。
だれかおもしろい話をして笑わせてくれる人が来てくれたら。歌をきかせてくれる人がいたら。そんな刺激があったら気がまぎれるのにと考えることもありましたし、そっとしておいてほしいという内向きな気持ちもありました。
術後の痛みが疼うずくなか届いたのは、事故に遭う少し前に仕上げて提出していた文芸英訳の下訳が製本されたものでした。それを見て、時は流れていたのだと気づきました。病院にいる間は、時間の止まった世界に閉じ込められていたように感じていたのです。
もっとも、ベッドテーブルの上に置かれたその本を、腕を伸ばして手に取ることはできません。それでも、家族にペラペラとめくってもらうと、事故に遭う前の忘れかけていた自分の一部を思い出すような感覚になりました。
ああ、ここの訳、苦労したなあ。息子の足がワープロのコードに引っ掛かりコンセントが抜けて、夢中で打ち込んだ訳文があっけなく数ページ分消えて泣きそうになったんだっけ。あらためて翻訳の苦労があれこれ思い出されました。子育てが一段落して、思いきって挑戦した初めての翻訳。苦労はしたけれど、充実した日々だったなぁ、そう思うと同時に、こんな声が自分のなかから聞こえました。
しかし、今の自分はどうだ? ペン1本握れない……。
そのうちベッド上でできるリハビリがノルマとなりました。4人部屋のカーテンを閉め切り、なぜかこそこそと隠れて、一人でメニューをこなしていました。こんな身体になってしまった自分が情けない。痛みに耐える姿を見られたくない。この期に及んでそんな見栄は捨ててしまいたいのに。悶々とした孤独な日々が続きました。
事故に遭ってから2ヶ月後、やっと1泊の外泊許可がおり、自宅に戻ることができました。玄関先のたった3段のステップを上れないことに、ショックを受けました。寝たきりの生活が長かったせいで、足腰の筋力がかなり落ちていたのです。1段足をのせるたびにぐらりとふらつき、娘につかまってなんとかリビングルームのソファにたどり着いたのを覚えています。
自分の身体ではないかのような感覚は病院に戻ってからも数日続きましたが、動くうちに、やせ細った足ながら、院内の移動は一人でできるようになっていきました。理学療法室へ通ってリハビリを行うようになると、ようやく萎えた手足の筋力が少しずつ戻ってくる手応えを感じるようになりました。ペン1本握れない自分から脱却しよう。回復が実感できるようになると、そんなふうに意欲が少しずつ芽生えてきました。
家族が入院するということ
意識が戻りはじめた当初、家族は大変な毎日を過ごしていたはずなのに、私はといえば朦朧としたまま、家族の生活への影響の大きさには思いが及びませんでした。動かない身体に、「なぜ?」と自分の辛さばかりを恨む日々でした。
子どもは救命救急センターに入れないからと、娘と息子は、メッセージテープをせっせと届けてくれていました。病棟に移ってからも、下校後、毎日お見舞いに来てくれました。
「私ね、覚悟したんだよ、あのとき」と中学2年生だった娘が語ったのは、退院して随分経ってからでした。母のいない日々をどんなふうに過ごしていたか、話せるタイミングを待っていたのだと思います。小学校4年だった息子も幼いながら、身の回りのことをできる限り自力で頑張っていたようです。
日常は一変し、当たり前の存在が当たり前でなくなる。
一つだった生活の場所が二つに分かれ、それぞれが孤独と隣合わせになる。
話したかったことも、楽しみにしていたことも封印しなくてはならなくなる。
自分のことは自分で解決しなくては、もっと頑張らなくては、我慢しなくては、と一人ひとりが自分を追い詰め心に蓋をしてしまう。
家族が入院するというのは、そういうことなのだと思います。
なにもできない自分
退院してからは週に5日間リハビリに通いました。毎日1時間みっちりのメニュー。負けるものか! 動けるようになるんだ! リハビリをしていると、空虚だった気持ちが少し和らぐのですが、帰宅すると決まって虚しさに襲われました。
「リハビリ以外、何もしなくていいから」
「とにかく、危ないからじっとしてて」
「いいから、いいから。ソファで休んでて」
少しでも手伝おう、リハビリにもなるからという思いで台所に立つと、家族にそう言われてしまう。家族に優しくされればされるほど、むしろあてにされない虚しさを感じてしまうのです。家族はそんなつもりはまったくないはずなのに、まるで邪魔だから自分の動線を妨げないでくれと言われているような卑屈な思いさえも襲ってきました。
動けない自分、動くことを制止される自分。
当たり前にこなしていた家事も、時間をかけてやっと洗濯物を片手でたたむくらいがせいぜいのところ。
自分は役立たずの価値のない人間に成り下がった。
家事もできない、子どもの面倒も見られない。
帰るなりバタバタと忙しそうに動き回る家族のなかで、身の置き所が見つからない。
自分が情けなくちっぽけに思えて、涙が出ました。
(注)ウェブ掲載にあたり、可読性向上のため、改行を加えています。
バナーイラスト:イスナデザイン
〈編集部より〉
入院生活では、元気だった過去や先の見えない未来にどうしてもとらわれてしまいます。日常を支えていた「自分のやりたいこと」「できること」が、入院生活では当たり前ではなくなるのです。長期入院する子どもたちと出会ったとき、著者はそんな自分の経験を思い起こします。それが、過去でもなく、未来でもなく、「今」に没頭する時間を届けるという活動につながりました。その思いはどのように実を結び、変化を生み出したのか──。ぜひ本書を手にとってみてください。
〈関連記事〉
『夢中になれる小児病棟――子どもとアーティストが出会ったら』
松本惠里著、英治出版、2021年6月発売
「今」に没頭する時間が、子どもを、親を、病院を変えた──。
病気や障がいがある子どもに、アートを届けるNPO。
孤独や未来への不安、治療の緊張感のなかで、「患者ではない時間」が生み出したものとは?
〈目次〉
第1章 患者になってわかったこと
第2章 院内学級という原点
第3章 子どもとアートが出会うために
第4章 子どもが変わる、家族が変わる、現場が変わる
第5章 支援されるだけじゃない!
第6章 その先の支援へ
おわりに──笑顔のサイクル
〈著者〉
松本惠里(まつもと・えり)
認定NPO法人スマイリングホスピタルジャパン代表理事。外資系銀行勤務ののち、子育て中に教員免許取得。2005年東京大学医学部附属病院内、都立北特別支援学校院内学級英語教員に、09年国立成育医療研究センター内、都立光明特別支援学校院内学級同教員に着任。病院の子どもたちと過ごした経験をもとに、12年、病いや障がいと闘う子どもたちをアートで支援する団体、NPO法人スマイリングホスピタルジャパンを設立。


