
学びに「喜び」と「誇り」を⾒出す学校とは?〜「美しい作品(beautiful work)」とPBLの最先端【『⼦どもの誇りに灯をともす』対談イベントレポート】
2023年3月に発刊された『⼦どもの誇りに灯をともす』は、アメリカの小さな学校の教師だったロン・バーガーの教育思想が詰まった一冊です。全米屈指のPBL(プロジェクト型学習)校、ハイ・テック・ハイにも影響を与え、現場の教師に20年読み継がれてきました。
クラスメートから批評してもらい、何度も推敲を重ねてつくりあげた美しい作品(beautiful work)をみんなの前で発表する。プロジェクト型の授業を通して生き生きと学ぶようになる子どもたちの姿が本書には描かれます。
⽇本の教育現場でも、プロジェクト型学習が取り⼊れられるようになりました。⼀⽅で、本当に⽣徒の深い学びを引き出せているのか、⽣徒たちが喜びを感じているのか、課題感を持つ教師の方々もいるのではないでしょうか?
本イベントでは、⽇本とアメリカの教育現場に携わる3⼈をゲストに迎え、⼦どもたちが学校の学びの中で「喜び」と「誇り」を⾒出すための視点やヒントについて語り合っていただきました。(文:渡邉雅子、写真:英治出版)
プロジェクト型学習の現場で愛される本との出会い
イベントが行われたのは3月末日。平日の夜にもかかわらず、公立学校からオルタナティブスクールなど多様な学校の教員から教育関係者、保護者まで、オンラインを含めると60人以上の方が参加していた。
ライターの私も、小学生の子を持つ親の一人として「これからの教育のあり方」に興味があり、参加することに。(本記事では “教育に漠然とした興味がある”私のつぶやきを副音声的に交えてお届けします)
藤原 さと:こんばんは。私は本書で解説を担当しています。初めて原著に触れたのは経産省の事業で、ハイ・テック・ハイというPBL校の教員研修プログラムの日本導入に関わっていたときのことです。
「すごく大切なエッセイだよ」と言われて、読んでみたら、少し不思議な感じがしました。そこにあるのは「物語」で、方法論は書かれていないんです。ただ登場する子どもの姿が生き生きとして印象的で、「これは大事な本だ」と惹きつけられたのを覚えています。
塚越さんは、ハイ・テック・ハイの先生方が来日して日本の教員向けにワークショップをした際、通訳してくださったご縁があり、本書の出版に際してもぜひと翻訳をお願いしました。

一般社団法人こたえのない学校代表理事。
ハイ・テック・ハイの教員研修プログラムの日本導入にも携わる。
塚越 悦子:そのワークショップの翻訳を通してハイ・テック・ハイについてより深く知ることができ、今は3人の息子がハイ・テック・ハイに通っています。私はアメリカ在住で昨日、成田に到着したのですが、出発前日に運良く、著者のロン・バーガーに会うことができて。ロンは日本の美意識をリスペクトしていて、日本にもぜひ行きたいと話していましたよ。

翻訳家。本書の翻訳を担当。
3人の息子がハイ・テック・ハイに通っている。
藤原:また、高橋先生とは経産省の事業で、2018年にハイ・テック・ハイの現地視察に行きました。埼玉県戸田市は「戸田型PBL」として知られるようにプロジェクト型学習を推進しています。私も視察に伺いましたが、子どもたちが作品を10回以上つくり直したり、「なぜこれをやっているのか」などの質問に答えてくれたりする姿が印象的でした。
高橋 博美:ハイ・テック・ハイの現地視察は怒涛の3日間で、本当に多くの刺激をいただきました。それから数年を経て、現在は戸田東小学校の“CEO”という形でやっています。当校は普通の公立小学校ですが、校内研究という文化があり、プロジェクト型学習に力を入れています。今日はよろしくお願いします。

戸田市立戸田東小学校長。
PBLを推進し、その全国に先駆けた取り組みで注目を集めている。
この後、会場では塚越さんがハイ・テック・ハイの、高橋先生が戸田東小学校の、プロジェクト型学習の事例について、写真を交えて紹介してくださった。
PBLでどんなことをやっているのか知らなかったけれど、高橋先生のお話のなかに「妊婦さんやお年寄りの困りごとを解決するため、子どもたちが当事者にヒアリングしたり、町工場の方のアドバイスをもらったりしながら試行錯誤を繰り返してものづくりする様子」の紹介があり、なるほど……と私も少しずつ手触り感を持ち始める。
失敗したとき、大人がどう動くかを子どもは見ている
3人のトークは、本書の原題にも入っている「倫理」観を軸にスタート。
藤原:さて、『子どもの誇りに灯をともす』の原題は“An Ethic of Excellence(エクセレンスの倫理)”ですね。「エクセレンスの倫理」というと抽象的で、難しいなと感じていて。今日はそれが現場では具体的にどう現れているのかお二人に伺っていきたいと思い、いくつか問いを用意してきました。
一つ目は「どんなときに、子どもたちは倫理観を培っていると感じるか?」。私自身は学校に「これは正しい/間違っている」と言われて育ち、「自分はこれが正しいと思う」と主体的に判断する機会はあまりなかった記憶があって。どんな出来事を通して、子どもたちは自ら「これはよいこと/悪いこと」と判断する力を育んでいくのか。いかがでしょう?

塚越:難しい質問ですね。わが家は、2019年までの5年間を日本で過ごし、当時3兄弟は日本の学校に行きました。三男は日本の小学校に半年通ってアメリカに渡り、小2〜小5現在までハイ・テック・ハイに通っています。
先日、三男がクラスメートから、アジア人であることをからかわれて。その件は学校に重く捉えられ、からかった子には “Day of Reflection”として校長先生やサポートの先生と一日考える時間が与えられたり、クラスや学年、学校全体でもこの件について話がされたんです。
三男はこれに関して「ハイ・テック・ハイはインクルーシブで差別がないと言っているけど、それは本当じゃないよ」と言ったんですね。ただ私はそれに対して、「差別がない、いじめがないと言っているわけではなくて、『そういう場所をつくりたい』と言っているんだよ」と伝えました。
言ってみれば“理想”ですが、理想があって、実際とかけ離れているならばそれを真摯に受けとめ、何ができるかを考えることが大事。だから「理想を掲げるのは意味がない」は、違うと思ったんですね。実際その後、三男の友達数人が「お互いを尊重しましょう」と呼びかける全校集会を、校長先生に提案してくれました。
だから、「これが目指すべき姿だ」を掲げるのは大事だし、理想とギャップがあるとき、大人たちが何をするか、子どもたちはよく見ている。倫理観は、理想を掲げ、それに対して実際に何をやっているかというところで育まれるものなのかなと思います。
高橋:私たちの学校では教育目標として「自分が好き」「人を大切にする」「未来をつくる」の3つを掲げ、それぞれ繰り返し、朝会で話すようにしています。「人を大切にする」も月に1度は話していますが、それでも、いじめや差別は起きるもの。いじめだけでなく、最近ではデジタル・シティズンシップにまつわるトラブルもありますね。
いずれにしても私たちは、事件や失敗が起きたときはチャンスでもあると考えています。大切なのは、頭ごなしに怒ったり、禁止したりするのではなく、「こういうことが起きてしまったけれど、どうしたらいいと思う?」と子どもたちに問いかけること。クラス全体で話し合い、みんなでいい文化をつくっていくなかで、倫理観は培っていけると思っています。
藤原:本書にも「モデル(模範)」という言葉がありますが、お二人の話にもあるように、先生方の姿──日頃の眼差しや、トラブルが起きたときの態度などが模範になることはあると思います。生徒たちは意識する、しないにかかわらず、そうした先生の姿を見て、模倣していくと思う。そのなかで、倫理観も培われていくのではと感じました。
なおモデルに関していうと、著者であり教師のロンは、すごく愛情を持って子どもたちの美しい作品を「モデル」と呼んで持ち歩いているんですよね。ロンには、「この子のいいところを僕はわかる」と、批評する目に自信があるような気がします。書籍には「すべての人がよき批評家になるべき」という指摘がありますが、誰かの作品に対して「私にはこのよさがわかる」という目を持つことで、倫理観や美的感覚が養われる面もあるかもしれません。
“I respectfully disagree”の流儀
ところで、「エクセレンスの倫理」の前提である「エクセレンス」の意味を、私はつかみきれずにいた。辞書によると「excellence」は卓越、優秀とあるが、本書ではそれ以外の意も込められているようだ。すると会場からもこんな質問が。
会場から: 書籍のなかで「エクセレンス」という概念は人としてエクセレンスであること、社会にとってかけがえのない人であることだと広く捉えられる、とありましたが、いまいち理解できませんでした。この言葉を体現されていると思ったエピソードがあればお聞きしたいです。
塚越:例えばハイ・テック・ハイでは、高校生になると先生をファーストネームで呼ぶ文化があり、先生と生徒の距離がとても近くなるんです。背景には、生徒が先生に相談したいと思ったとき、相談するハードルを下げる意図があるようです。
先生は「絶対的な専門家で、何かを教えてくれる人」というより、必要な時に「対話してくれる存在」として位置づけられていると感じます。
そのおかげで、生徒たちは、先生に対し「自分はそう思わない」ことも
発言しやすい風土があります。子どもたちがディスカッションのやり方を学ぶ場があるのですが、そこでもまず“I respectfully disagree(敬意をもって、でもあなたの意見に反対します)”という言い方を教えられるんですね。
「自分はこう思う/思わない」の表明が奨励されている環境は、倫理的に何がよいことなのかを考えたり、時に話し合いながら自分の中でも探っていく、そんな土壌ができる理由の一つではないかと思っています。
塚越さんの “I respectfully disagree”という言い回しを聞きながら、私は書籍の「解説」に藤原さんが書かれていた一節をふと思い出していた。
“「エクセレンス」は卓越とも翻訳されることが多いが、元を辿ると古代ギリシャ語の「アレテー」という言葉に辿り着く。この言葉には「卓越」だけではなく「徳」の概念も含意される。
よってエクセレンスといった場合に、単に人より秀でることを目指すのではなく、同時に善き生を目指し、倫理観を養っていってほしいという思いが込められていることに注意したい。子どもたちが、粘り強く良い作品をつくり上げることは、善き人格を形成するということと同義なのだ。” (『子どもの誇りに灯をともす』p.254)
エクセレンスの源にあるのはやっぱり、単純な“優秀さ”ではなく、人としてよくあるべしという“徳”の概念なのかもしれない。
「誰かのため」に、試行錯誤を繰り返す
藤原:次の問いは、「『美しい作品(beautiful work)』をつくるとき、推敲を繰り返すなかで子どもたちはどのような力を育んでいると感じるか?」。ロンはつくれれば何でもいいとは考えていなくて、試行錯誤を重ねて本当によい作品をつくることを大切にしています。その過程で育まれるものをどうお考えですか?
塚越:次男がハイ・テック・ハイで障害のある方のためにゲームコントローラーをカスタマイズするプロジェクトに取り組んだとき、やっぱりコントローラーを何度も何度もつくり直していたんです。
それは、目の前にそれを待っている人がいる、というモチベーションが大きかったと思います。そして、自分たちのつくる作品が完璧でないと機能しないことも明らかでした。子どもたちは、自分たちがこのコントローラーをつくることが実際にその人にとってどういう意味をもつのか、学んだと思います。
高橋:私たちの学校でも「ペルソナを決める」といって、「誰のために何をするのか」の話し合いに時間をかけます。試作品に対しても「これはいいね。だけど、これでその人はうまく使えるかな?」と問いかけることで、子どもたちは「じゃあ次はこうしよう」と意欲を持って試行錯誤を続けますし、完成度の高いものづくりを目指すようになります。
担任の先生が一人でいくつものプロジェクトに寄り添うのは難しいので、積極的に外部の方の力もお借りするようにしています。例えば高齢者向けのプロダクト開発なら、ご高齢の方をゲストに招いて、質問をする。最初はゲストの方々も遠慮があるんです。でも何回か来てもらい、子どもたちが改良を繰り返す様子を見ると、ゲストも率直なフィードバックをくれるようになります。
「一回ぽっきりじゃない。失敗したらやり直せばいいし、何度も試行錯誤をしないといいものはできない」ことを学びながら、最終的にはよいものをつくるという経験ができていると感じます。

藤原:ペルソナをはっきりさせて、愛情を持って接することは、推敲を繰り返す原動力になりますね。「顔の見えるこの人」に対して何かしたい、80点ではなく120点のものをつくってあげたい。学校にもそんな文化ができていくといいですね。
顔の見える相手のために、という話を聞いたとき、本書の帯にある “「提出して終わり」じゃなくて”というフレーズがすとん、と腑に落ちた。
ものづくりの先には、それを使う“誰か”の存在がある。その存在との関係が近いほど、熱量をもって完成度の高いものをつくりたくなるのは、自然なことなのかもしれない。
ただ「褒める」では、自己肯定感は育まれない?
そして話題は「自己肯定感」へ。これは子育てでもなにかと登場するキーワード。子とどう接するのがよいか模索している親は多いと思うし、私もその一人だ。
藤原:最後の問いは、「子どもたちの自尊心はどのように育まれるか?」です。
塚越:私は以前、『アドラー流子育てベーシックブック』(サウザンブックス社)の翻訳をしたのですが、アドラー流の子育てコースの講師になるトレーニングをした際、先生が自己肯定感を持つために必要なことが二つある、と話していたんです。一つは愛されていること、そしてもう一つが、“feeling capable”、つまり「自分にはできる」感覚を持つことだと。
『子どもの誇りに灯をともす』を初めて読んだとき、とても印象的だったのが、「子どもたちを単純に褒めることでは自己肯定感が育まれない」という部分だったんです。
ロン曰く、「自分であまりうまくできていないと思うことを褒められても、自己肯定感を育てることにはならない」。自己肯定感は「本当にいいものがつくれるようになっていく過程で育まれる」から、必要なのはそれをサポートすることだと。つまり「自分には本当にいいものがつくれる」という“feeling capable”ですよね。当時の先生の話に通じるなと思いました。
なるほど “feeling capable”……。「ありのままを愛する」はまず大事なこととしてよく聞くけれど、それだけでは自己肯定感は育まれないらしい。
塚越:わが家は毎日、息子たちの送迎中に車でいろんな話をします。あるとき、“Do you love yourself(自分のことが好き)?”という話になって。上の二人は「好き」と答えて、三男は「好きじゃない」と答えたんですね。
本人たちにも聞きながらその理由を考えてみたら、上の二人は学校や習い事でいろいろな経験をしてきて、「自分はこれが得意」というものをはっきり持っていることが大きいと感じました。対して三男はまだ探している途中なのかなと。
もちろん「そのままのあなたを愛しているよ」は全力で伝えるようにしていますが、やっぱりそれだけではないんだなと。「自分はこれができる」と言う自信があることは、“love myself”にとても大事だし、三男にもそのサポートをしていきたいなと思っています。

高橋:当校の教育目標の一つにも「自分が好き」があります。「自分優先でいいのか?」と言われることもありますが、私たちは子どもたちに「自分が好き」と言えるようになってほしいのです。「短所も見方を変えれば長所である」といった話も含め、朝会で繰り返し伝えています。
プロジェクト型学習はチームで進めますが、チームの中にはいろいろな「得意」を持つ子がいます。「オンラインでゲストの先生とつながろう」とコミュニケーションが得意な子もいれば、「それならこうするといいよ」とパソコンやタブレットの扱いが得意な子もいる。自然と役割分担がなされて、お互いに「ありがとう」と言える形ができてくるんですね。
藤原:チーム内での役割分担で「これは得意じゃないけれど、僕には他にできることがある」と感じられるのもまた、“feeling capable”ですね。
私は重い障害のある子どもたちの親御さんと一緒にインクルーシブ教育のプロジェクトをやっているのですが、例えば話すことも車椅子から立ち上がることもできないような子であっても、愛情を注がれ、「私には○○ができる」という信念があれば、自尊心は育めるはずなんです。本書の中でも学習障害のある子や、ろう学校の子どもたちが登場しますが、ロン自身も、そうした信念を強く持っていると思います。
日本の教育の“美”もある──伝統と革新の融合へ
ここまで交わされてきたような話を、日本で暮らす一人として、また日本の学校に子を通わせる親として(またはそこで働く先生方として)、どんなふうに考えていったらいいんだろう? 会場でも、日本にフォーカスした質問があがった。
会場から:「先生がモデルになる部分もある」とのお話もありましたが、自尊心に関しても、先生が「自分を好き」でいる姿勢を見せていくことは大事だなと感じていて。日本の学校に対する批判も多い近年ですが、「日本の学校や先生のこういうところは素晴らしい」と思うことがあればお聞きしたいです。
塚越:アメリカに帰ったとき、日本のように音楽や美術の授業が当然のように受けられるのは実は素晴らしいことだったんだなと思いました。アメリカの公立校は地域によってクオリティの差が大きく、音楽の授業がないところも珍しくありません。音楽の授業があっても、PTAがファンドレイジングをして音楽の先生を雇っている状況だったりするんですね。
また、三男はハイ・テック・ハイで「なぜ子どもたちは先生の言うことを聞かないのか」と言っていたことがあります。日本の学校では「静かにして先生の話を聞く」など、基本的なマナーをもっと教えていたと。規則で縛りすぎるのもいいとは思わないですが、大事なのはバランスで、どちらも見習うべきところはあるのだと思います。
高橋:日本の教育のよさはありますよね。小学校では、担任が30人前後の子どもを抱えて、一生懸命「どの子の可能性も伸ばしたい」と思ってやっている。30人を集団としてまとめながら、「みんなで」よい学級文化をつくる。一方で、全員をある程度まで上げていこうとすると、結局はボリュームゾーンの「真ん中」に合わせた授業になってしまう、という課題もありますが。
また、担任が体育や図工などを含めて横断的に見ることで、それぞれの子のよさを見つけて褒めて伸ばせるよさもあると思います。
藤原:私は中3の娘がいて、小1〜小3の頃はアメリカの現地校に通っていました。当時、周りに日本人のお子さんも何人かいましたが、「日本の学校のほうが向いている子」もやっぱり一定数いるんですよ。
アメリカの学校でたくさん泣いていた子が、日本に帰ったら水を得た魚のように生き生き学校に通っていたりとか。一方で娘はアメリカの学校が大好きで、日本の学校のルールに不満があるタイプ。だからPBLも絶対に正しいわけではなく、向き・不向きがあると思います。
ちょっと視点を変えて「日本の教育とは何か」を考えると、私は「取り戻してみたらいいのでは?」と思うことがあって。いまの「学制」が入ってきたのは明治時代。以降は学習指導要綱で定める「正解」を習得した子が偉いような感じがありますが、江戸時代まではもっと多様だったと思うんですよ。
想像ですが、藩校や私塾では、先生の姿が圧倒的によかったのではないか?と思います。「よき師の姿」はその場の文化をつくり、そこに生徒たちが来て、いいものをつくろうと切磋琢磨する。欧米は言葉や概念に頼る傾向があるのに比べ、日本はもともと茶道や武道など「師の姿や立ち振るまいを見て学ぶ」文化がある。そこへ立ち戻ってみるのもありでは、と感じますね。
会場から:日本の学校という視点で、もう一つ質問があります。学校に文化を根付かせていくのは時間がかかりますが、校長は2、3年で入れ替わることが多い。そんななか高橋先生はご自身の学校にどうやって文化を根づかせていらっしゃるのでしょう?
高橋:よく「校長が変わると学校が変わる」と話題になりますが、属人的なあり方ではその人がいなくなったら終わってしまうので、校内に文化を根づかせることは大事ですね。
そのためにしていることは、仕組みづくりと、理念を言い続けること。学校の方針は、校長が最初の職員会議で言ってそれっきり、のこともありますが、私は職員会議のたびに学校の方針の資料を見せながら、「これがミッションですね」としつこいくらいに言い続けています。
学校の方針に最初から強く共感する職員は、全員でなくてもいいと思うんです。20%の職員が「これって大事だよね」と思えば、60%くらいの職員もそれを「いい」と思い、学校の文化になっていく。ちなみに戸田東小学校は、前任の校長がこうした文化を根づかせてくれ、私はその方針を受け継いで、職員にも継続して伝えていくことができている。この後にまた校長が変わっても、持続していくのではないかと思います。
塚越:日本の学校でも、プロジェクト型学習を取り入れているところは増えてきていますよね。長男も小5のとき、日本の学校でやった「お箸のプロジェクト」という教科横断型プロジェクトが印象に残っているそうです。
その後ハイ・テック・ハイでの経験もあり、彼はいま「教育」に興味があって。「日本の高校でももっとPBLができるんじゃないか」「日本の高校がどんなところか知りたい」という思いから、ちょうど今、日本に短期留学を検討しているところです。だから日本の学校、先生方にもすばらしいところはたくさんあると思っていますし、外のよいところも取り入れながら、今後もぜひがんばっていってほしいなと思います。
そういえば書籍の中にも、「先生がワクワクしていれば、生徒たちもワクワクする」という言葉が紹介されていた。同時に、教師として長く勤めるほど、環境によってはそうした熱量を持ち続けることが難しい、という話も。(『子どもの誇りに灯をともす』p.216-217)
一方、年月を重ねても、ロンのように新鮮な気持ちで学び続け、熱量を保てる人もいる。その背景のひとつに「世界とのつながりを失わず、学校内外と協働したり、刺激にワクワクする」大切さがあったことを思い出す。この日、このイベントに多岐にわたる教員の方々が多く参加されていることが、希望だと思った。
イベント後には交流の時間が設けられ、学校や役職等の枠を越えて、これからの教育について熱く語り合う様子が見られました。
今回のイベントで触れた話題は書籍のほんの一部です。ロン・バーガーが教育の現場で体験したたくさんのエピソードを通して、彼の教育思想により深く触れてみたい方は、ぜひ書籍をお手にとってみてください。
<著者ロン・バーガーから日本の読者へビデオメッセージ>
<登壇者プロフィール>
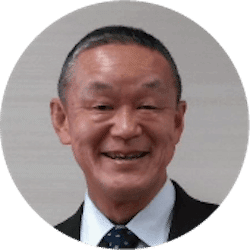
高橋 博美(たかはし ひろみ)
戸田市立戸田東小学校長。埼玉大学教育学部卒業。埼玉県公立小学校教員を20年勤め、埼玉県立総合教育センター指導主事、戸田市立小学校教頭、戸田市立教育センター所長を経て、2015年戸田市立笹目東小学校長。2018年、FutureEdu Tokyoとこたえのない学校による経済産業省「未来の教室」実証事業でサンディエゴにあるハイ・テック・ハイの視察研修に参加。2022年から現職。36学級、1,137名の児童という大規模校で、「20年後の社会で活躍できる子の育成」を掲げ、PBLを学校課題研究として全教職員で取り組む。年間37回もの視察を受け入れ、全教員が交代で授業公開を行っている。

塚越 悦子(つかごし えつこ)
翻訳業。カップル&パートナーシップ専門コーチ、アドラー & 幸福学ハッピーペアレンティング(子育てコース)講師。東京大学文学部卒業、モントレー国際大学院行政学修士。国連勤務やJICAコンサルタントを経て2002年に渡米。日本語補習授業学校の事務局長として勤務し、バイリンガル教育に関わる。アメリカ生活で夫婦関係や子育てに悩む人が多いことを痛感し、ライフコーチの資格を取得。また、出産をきっかけに受けたアドラー心理学をベースにした親子コミュニケーションコースに感銘を受け、インストラクターの資格を取得、サンディエゴでセミナーを行ってきた。三子がハイ・テック・ハイに通学中。著書に『国際結婚一年生』(主婦の友社)、訳書に『異性の心を上手に透視する方法』(プレジデント社)、『アドラー流子育てベーシックブック』(サウザンブックス社)。

藤原 さと(ふじわら さと)
一般社団法人こたえのない学校代表理事。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、コーネル大学大学院修士(公共政策学)。日本政策金融公庫、ソニーなどで海外アライアンス、新規事業立ち上げなどを経験。仕事をしながら子育てをするなかで「探究する学び」に出会い、2014年、一般社団法人こたえのない学校を設立。小学生向けの探究型キャリアプログラムを実施するほか、学校教育に携わる教師と学校外で教育に携わる多様な大人が出会い、チームで探究プロジェクトを実施する「Learning Creator's Lab」を主宰。2018年、経済産業省「未来の教室」事業の採択を受け、世界屈指のプロジェクト型学習を行うハイ・テック・ハイの教員研修プログラムの日本導入に携わる。著書に『「探究」する学びをつくる』『協働する探究のデザイン』(平凡社)など。
<記事構成・執筆>

渡邉 雅子(わたなべ まさこ)
フリーライター。早稲田大学卒業後、PR会社勤務を経てフィジー留学。豪州にてワーキングホリデー中、現地の日本人向け冊子の編集部でライターに。帰国後は都内ベンチャー等を経て独立。2016年より福岡。現在は糸島近辺を拠点に、企業の取材執筆から日常エッセイまで広く活動。いろいろとマイペースな娘と暮らすなか、教育・学びのあり方への関心も上昇中。

